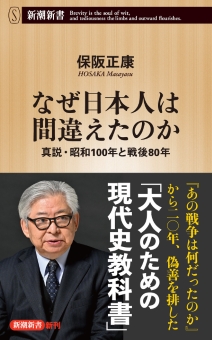書評
2025年8月号掲載
ジャーナリストの史観、ここに極まる
保阪正康『なぜ日本人は間違えたのか─真説・昭和100年と戦後80年─』(新潮新書)
対象書籍名:『なぜ日本人は間違えたのか─真説・昭和100年と戦後80年─』
対象著者:保阪正康
対象書籍ISBN:978-4-10-611094-8
歴史取材の鬼たる著者の「昭和一〇〇年」と「戦後八〇年」に向けての魂の叫び。しかも一字一句が重い。長年の取材の蓄積に裏打ちされているからだ。幾ら書物を漁り、公文書を調べても、耳に届かぬだろう声が、どの頁からも溢れ出る。特に近代日本の戦争に絡むことにおいて。
とはいえ、著者は1939年生まれだから、取材できる声の主は戦後に生き残った人々にもちろん最初から限られてきた。でも著者は自信を持って書く。「もとより死んだ者の肉声は聞けないが、それでも死者の声が聞こえてくる。妙な言い方だが、生者の声を長く聞いていると、その声が目の前にいる一人ではなくて何人もの声を代表していることがわかる」。保阪流の取材の極意であろう。これぞ真の聴く力だ。特定の理屈や史観による学者的予断を排し、周辺をよく調べ、相手の立場を想像し、自己の思い込みを滅して聴く。そういう作業を繰り返していると聞こえてくるものなのだろう。そうやって著者は、歴史の膨大な破片、ミクロな声を拾い集め、その声を聴いた実感を活かしながら歴史を編む。アカデミストではなくてジャーナリストによる歴史の書き方の理想と実践だ。そのひとつの見事なまとめが本書。扱われる内容は多岐に及ぶ。でも決してとっちらかってはいない。著者ならではの生き生きとして剛直な縦糸が幾筋か通り、全編が有機化して骨太な声になる。
縦糸の一本はたとえば「原価計算」。著者は言う。英国の植民地支配は常に原価計算の上に成り立っていたのだと。中国に対しても決して面の支配を試みなかった。上海や天津を点で支配し、面の富を点に集め、事実上の面の支配に結びつける。本当に面を征服しようとしたら、軍隊が幾らあっても足りない。中国は奥深過ぎる。コスト高だ。減価償却のできない植民地を支配したがる馬鹿が何処にいる? それが居た。日中戦争のときの日本である。特に日本陸軍である。面の征服にこだわった。なぜか。著者の本領が発揮される。陸軍全体が愚かという大雑把な議論はしない。あくまでミクロに。日中戦争のときの軍の若手・中堅幕僚層は大正後期以降に陸軍士官学校で学んだ世代。1922(大正11)年卒業の第三四期生だと、三五〇人中、五〇人以上が中退したという。大正デモクラシーの影響だ。普通学校の同世代の学生とさかんに交際し、人文書や社会科学書も読み、軍に疑問を感じて辞める者が続出。大変だ。軍組織が持たぬ。人文書や社会科学書を読むな! よその学生と付き合うな! この反動期以降の軍事純粋培養世代が戦時の陸軍の中間管理職を覆い尽くしていった。陸軍が政治や経済に発言力を高めていくときだというのに。しかも昭和10年代の陸軍の上層部は、派閥抗争の末、東條英機とその仲間たちに握られてゆく。そこで著者はダメを押す。東條は「思想書や人文書をまったく読まずに生きてきたと秘書は証言する。だから人間の心理、文化や思想は皆目わからなかった」。東條個人のパーソナリティと世代論が重なり、陸軍は現実を観られなくなったのだ。原価計算も中国への理解もあったものではない。目から鱗の落ちる陸軍史ではないか。
では戦時の日本の軍部は冷静な損得勘定と全く切り離されてしまっていたのだろうか。そうでもあるまい。著者は海軍に昭和10年代に存在した「短期現役士官制度」にその後の歴史の起爆剤を見いだす。「法学部や経済学部出身で、大蔵省や大手銀行などに勤めて間もない優秀な若手」を海軍は集めて、「彼らを主計将校にするために短現コースで鍛え上げた」。具体的には何を? 海戦における敵味方の損害を金銭に換算して損得勘定をする。あるいは損害を受けた艦船を修理するのと相当する艦船を新造するのとどちらが得かを計算する。つまり原価計算だ。この仕事を通じて大日本帝国の軍備の無駄と虚しさに絶望した主計将校が、官僚に復帰して、軍の無謀さへの怒りをバネに戦後日本の高度成長を支えてゆく。著者によれば「高度成長期」の歴代大蔵事務次官の一三人のうち九人までが「短現」出身者という。
原価計算的思考の有無。たとえばこの縦糸一本で日中戦争から高度成長までが通るのだ。証言を集め、世代や個人を細かくミクロにつかまえ、大きな主語を小さな主語に取り換えて、それでこそかえって大きな視野が開ける。著者の方法だろう。
「昭和一〇〇年」と「戦後八〇年」に因んではいるけれど、そういう言葉が予期させる大きな物語を徹底的に裏切るのが本書だ。常識のお膳をひっくり返そう!
(かたやま・もりひで 思想史家)