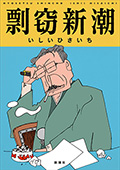書評
2025年8月号掲載
今月の新潮文庫
オールスターキャストで読む近代の女子教育史
柚木麻子『らんたん』
対象書籍名:『らんたん』
対象著者:柚木麻子
対象書籍ISBN:978-4-10-120244-0
物語はいささか意表を突く場面からはじまる。
大正最後の年(1926年)、渡辺ゆりはプロポーズされた男性に、ひとつの条件を出した。
〈私、河井道先生とシスターフッドの関係にあります。女子英学塾時代の恩師でもあり、親友でもある女性です。結婚しても、これまでどおり、彼女との仲を維持していけるのであれば、お申し込みを承諾します〉
ええーっと、それはどういう意味? ゆりはつけ加えた。
〈彼女と一緒に理想の女学校を作り、生涯をともにすることが私の夢なんです〉
ときに渡辺ゆりは三八歳。河井道は四九歳。ゆりに結婚を申し込んだ一色乕児は五一歳。ゆりによれば、シスターフッドとは〈イエス・キリストのもとに集う姉妹、つまりは血縁関係を持たない女性同士の絆を指します〉
ここからはじまる柚木麻子『らんたん』は、二人が理想の女学校を立ち上げるまでとその後の経緯を、女性史のオールスターキャストに近い多彩な人物を配して描き出した絢爛豪華な長編小説だ。物語の中心を占めるのは、作者の母校でもある恵泉女学園の成立史だが、女子教育の歴史が俯瞰できるスケール感!
女子教育界の第一世代として登場するのは、岩倉使節団の一員として六歳で渡米し、帰国後、女子英学塾(現在の津田塾大学)を創設した津田梅子である。本書では気難しい人物として描かれる梅子は、ともに渡米した山川(大山)捨松と学校を作るつもりだった。〈それなのに、あの人、帰国してすぐ結婚しちゃったのよ。それも、お父さんくらいのコブ付きのおじさんとね〉
そんな梅子の直系の弟子にあたる、いわば第二世代が主人公の河井道である。伊勢神宮の神職を務める家に生まれるも、一家で移住した北海道でキリスト教に出会って受洗。新渡戸稲造の紹介で梅子宅でしばらく世話になった後、梅子も卒業した米国のブリンマー大学に留学。帰国後、女子英学塾で教鞭をとるに至った。
梅子と道が教えるその女子英学塾に、生徒として入学したのが、第三世代にあたる準主役の渡辺(一色)ゆりだ。米国から帰国したばかりの颯爽たる道は生徒たちの憧れの的だったが、ゆりの行動は大胆だった。規律の厳しい寮を飛びだし、ゆりは道の家に押しかけるのだ。〈今日からここに置いてください。先生と一緒にここから学校に通います。なんでもやります〉
生活をともにする中で、いつか理想の女学校を作りたいのだと打ち明ける道。自分も教師になって必ず先生を手伝うと約束するゆり。ここを起点に強い絆で結ばれた二人が、実際に学校を立ち上げるのはずっと先、ゆりが結婚した後の1929(昭和4)年だった。
というのがメインプロットなのだけど、本書の魅力はそこにとどまらない。目玉のひとつは近代女性史を彩るスターが次々登場することだろう。
女子英学塾でゆりとともに学ぶ平塚明(らいてう)は学校でキセルをふかし、生意気な口をきいて梅子に退学を命じられる不良だし、後に社会主義者となる青山(山川)菊栄は在学中からキリスト教的人道主義の限界を指摘する論客だ。NHK朝ドラ「花子とアン」で描かれた、翻訳家の村岡花子と歌人の柳原燁子(白蓮)のシスターフッド的な関係にも、日蔭茶屋事件で知られる神近市子と伊藤野枝の愛憎劇にも新たな光が当てられる。
さらに胸がすくのは、当時の男性作家に道がもの申すくだりである。札幌時代からの友人・有島武郎の『或る女』に抗議する道も痛快だが、圧巻は道が梅子をけしかけて徳冨蘆花を訪ねる場面だろう。ヒット作『不如帰』に登場する継母のモデルは大山捨松で、その描き方に道は憤慨していたのである。かくて彼女はいい放つ。〈女を悪者にし、女を殺さなきゃ、読者の心も動かせないなんて、三文小説家だと言っているのです!!〉
シスターフッドという言葉は今日、すっかり定着したが、それは単純な「仲良し」ではなく、まして二人の関係を持続させるのは難しい。〈女同士の関係は永遠じゃないわ。結婚や恋愛で終わってしまうのよ〉という梅子の悲観的な持論は体験に基づいている。だが、その梅子も道とゆりの力を認め、最後には自身も『不如帰』によって歪められた捨松の名誉回復のために動くのだ。
縦にも横にもつながる女性同士のネットワーク。〈女同士が手を取り合えば、男は戦争できなくなるのにねえ〉という道の言葉は何を意味するのか、改めて考えたい。
(さいとう・みなこ 文芸評論家)