対談・鼎談
2025年9月号掲載
里見清一『患者と目を合わせない医者たち』(新潮新書)刊行記念
死にゆくひととどう話すか
川上未映子 × 里見清一
昨年母を看取った作家が、医療現場でさまざまに戦ってきた医師に問う、患者と医者の「新たな倫理」とは――
対象書籍名:『患者と目を合わせない医者たち』
対象著者:里見清一
対象書籍ISBN:978-4-10-611092-4

川上 二年半ほど前に母ががんだと診断され、その後本当にいろんなことがあって、昨春、母は亡くなりました。母の診断がくだった時、私は四十代半ばで、がんのことも医療経済のこともろくに知らずにいました。そこから里見先生の本を読み始め、こんなに医療に関する問題を網羅して、自ら悪役になることも厭わず、明確に答えや方向性などを示してくれるお医者さんがいるのかと感激して、多くのご本を読んできました。新刊の『患者と目を合わせない医者たち』(新潮新書)も本当に大切なことばかり書かれています。
里見 ありがとうございます。「週刊新潮」での連載をまとめたのですが、私はつい医療以外のことも――選挙とかウクライナなんかも――ど素人的に書くもので、医療に関する話に絞って新書にしてもらいました。
川上 いまは「どんな医療を受けて、どんなふうに死んでいくか」ということが、「どんなふうに生きるか」と同じ重さを持っているように感じます。というのは、母が予後の悪いがんだったせいで、私にとって、医師や医療が突然これまでとまるで違って見えてきたんです。例えば、私は最初、予後の悪いがんでも治してくれる「神のごとき医師」を求めていたし、その後も医師の顔色ひとつ、口調のわずかな変化にも一喜一憂してきました。これは私だけのことではなく、みんな、神とまでは言わなくても、できるだけいい医者に診てもらうために右往左往しているように思います。
里見 だから、すぐ「名医ランキング」なんて、いい加減な記事を載せる週刊誌が出てきますよね。みんな数字のデータに惑わされる。アメリカのある州で外科医が担当する患者の死亡率を公表したら、手術の成功率を上げるために複雑な病態の患者を避けるようになったそうです。
医者のすることは二つしかない
川上 先生が一貫して主張されているのは、いい医者とは何か、いい患者とは何かと問う以前に、医者も患者もお互いに倫理を持っていないとダメだということですよね。
里見 私なんかが言うのはおこがましいのでしょうけど。
川上 いまくらい進歩した技術があれば、誰でもいい医者にはなれるのですか?
里見 いや、みんなが求めているのは「病気を治してくれる医者」なんです。確かに、そんな医者になら、技術の進歩でなれる場合もあるかもしれない。でも、治す医者というのは必ずしも、川上さんなら川上さんの手を握って、おだやかに死なせてくれる医者ではありません。だいたいの外科医は手術をしてしまったら、言葉は悪いですが、「あとは俺たちの仕事じゃない」となります。実際、そこまで面倒をみていたら、次の患者の手術ができない。
川上 日本では外科でがんを切って、抗がん剤も外科がやりますよね。
里見 日本でもだんだん欧米的に抗がん剤は内科でやるようになりましたが、それぞれが分業化して、外科医がもう手術は無理だから内科に行け、内科医はやる薬が尽きたから次は緩和ケアに行け、となってしまう。問題なのは担当(だった)医者が「もうやることがないから緩和ケアにでも行け」なんて言い方をしてしまうことです。「俺たちはもう診ない、あなたの世話はしない」という宣言と「緩和ケアに行け」がイコールになってしまっている。
川上 ご本の中にも、がんが転移して、内科医から「今からホスピスを探しておくように」と言われ、激怒した患者のエピソードがありました。
里見 あの患者さんはがんセンターから私のところへやってきて、それから七年、ほとんどご自宅で暮らし、趣味の山歩きやカメラを楽しまれていました。治療はがんセンターのと同じことをやっただけですけどね。
川上 がんの当事者家族としても、「緩和ケアに」と言われてしまうと、(もう、何もすることがないのか、おしまいか……)と思ってしまって辛いんです。言葉の持つイメージの問題が大きいと思います。
里見 緩和ケアというのは、みんなが日常的にやっていることなんです。そもそも、医者のすることは二つしかありません。ひとつは寿命を延ばすことつまり延命で、もうひとつは対症療法です。どんな治療もこの二つに含まれます。病気を治してもいつかは死にますから、それまでの延命です。延命治療と対症療法はまったく別の話で、それぞれ独立してます。患者が「痛い、苦しい」と言いながら、寿命だけは延びる場合もあるわけですからね。一方、対症療法というのは、例えば風邪をひいて咳がひどい時に咳止めの薬を飲むように、寿命を延ばすとか縮めるとかとは関係がないけれども、楽にはできる。緩和ケアにおいても、例えば肺がんが脳に転移して頭が痛む人に痛み止めを出すとか放射線を当てるとか、余命三ヶ月なら三ヶ月に変わりはないけど、だったら痛くない方がいい。
川上 先生が仰ったように、私たちはずっと対症療法をしてもらいながら生きているのだから、がん患者にとっての緩和ケアも治療のひとつだと周知されたら、「今やっているのは死ぬための準備ではなく、今を生きるための治療なんだ」って思えるかもしれない。じっさい、本当にそのとおりだし。
里見 日赤(日本赤十字社医療センター)みたいな病院が持っている緩和ケア病棟と、完全に独立型のホスピスと、二種類ありますよね。私は後者には懐疑的です。緩和ケア病棟の患者さんは、末期であればあるほど、病態が激しく変わる。すごく苦しい症状や痛みが当然出てきます。例えば心臓のまわりに水が200ccも溜まったら、とても苦しくなります。これはモルヒネを使っても、酸素を使っても、ましてや耳元で賛美歌を歌っても良くなりません。でも、病態に気がついて、きちんと診断して、ちゃんと針を刺して水を抜けばスッと楽になる。そんな緩和ケアの治療技術がない独立型ホスピスはけっこうあるようです。だから病院の中にある緩和ケア病棟のほうがメリットが多い。私は自分が緩和ケア病棟にお願いした患者さんは毎日、それまでと同じように回診し、顔を見に行っています。
告知することが「正義」になった
川上 母ががんだと診断された時、医師が「疑いがありますね」から始まって、「あなたは血管に奇形があるから、手術ができない」と告知しました。私と同じくらいの、つまり母にとっては子供のような年齢の医師でした。母は大阪のおばちゃんですから、すぐ「先生、そやったら私、あと何年ぐらいですか」って思わず聞いてしまったんです。すると医師は冷静な口調で「一年半ぐらいかな」と。患者にとって、人にとって、最も慎重に扱われないといけない言葉やコミュニケーションが、こんなふうになされるなんて、と衝撃を受けました。事実に即したって、まだ、がんと決まったわけではないから、普通は「いや、まだそんな段階じゃないですよ」とか「ちゃんと検査してから」と言うべきだと思うのですが。
里見 もちろん、そうでしょう。
川上 「一年半」という医師の一言は、わたしたちの今後のすべてを方向づける、衝撃の言葉でした。もちろん、患者にとっては生命にかかわる病気なんて一生に一度か二度の大イベントだけど、医師にしたら日に何十人と診る患者の一人に過ぎないことは、頭ではわかるんです。だから恨んでも仕方がない、あんなふうに言った医師のことはもう忘れるべきだ、いや、やはり絶対にあんなことを言ってはダメだと思うべきだ――告知について考えると、いつもあの瞬間を思い出します。里見先生はずいぶん以前から、がんの患者に告知をしていこうというお考えですよね?
里見 1990年、横浜の市民病院にいた頃、私と上司の部長と二人で「もう、さすがに言わなきゃいけないよな」と、肺がんの患者にきちんと「悪性の腫瘍」と伝えるようにしました。「がんですか?」と訊かれたら「そうです」と答える。当時は告知が珍しく、すごく非難を浴びました。
川上 患者にがんであることを伏せるのが常識だったわけですね。それを「もう、さすがに」と思われたのはどうしてですか?
里見 黒澤明の映画「生きる」みたいに、医者が教えなくても、本人がわかってしまうからです。隣にがん患者とわかっている人がいて、その人と同じ治療をやって、同じ副作用が出たら、察するじゃないですか? あるいは、自分はがんだと知っている患者が、まだ知らない患者に向かって「あんたもがんだ」と言ってしまうこともある。そんな事態が不用意に起きるくらいなら、前もって医者が本当のことを伝えたほうがいい。一方で、むしろ百パーセント治るような早期のがんはわざわざ告知して脅かすことはないかもしれませんね。治らないがんだからこそ、これからの人生設計のためにも正しい情報を告知せざるを得ないという考えですね。
川上 いまはそんな考え方が共有されてきたように思いますが、三十五年前は患者も慣れていないから――。

里見清一(さとみ・せいいち)
本名・國頭英夫。国立がんセンター中央病院内科などを経て日本赤十字社医療センター内科系統括診療部長。著作に『「人生百年」という不幸』『医学の勝利が国家を滅ぼす』『死にゆく患者と、どう話すか』など。
里見 ええ。告知したら、やっぱり何人もの患者さんが落ち込みました。その時、精神科に相談したら、「だって、先生ががんだって言ったんでしょ。それで落ち込むのは病気でも何でもない。きわめて正常な反応だから、精神科の対象ではない。がんを治してあげたらいいじゃないですか。そしたら良くなりますよ」と事も無げに言われた。本当に、飛びかかって首を締めたくなりました。当時の精神科は、告知されて落ち込むのは、正常人の反応で、うつ病でも何でもない、という理屈でした。最近は精神科も変わってきて、適応障害や本物のうつとして治療の対象になりますし、精神腫瘍学という言葉もできましたけどね。サイコロジー(心理学)とオンコロジー(腫瘍学)を合わせた造語ですが、これも緩和ケアの一種です。
川上 私は母のがんがわかってからの一年間、ずっと恐慌状態でノイローゼになっていました。「精神腫瘍科に行った方がいい」とずいぶん勧められたものです。当事者がいちばんつらいですが、当事者家族の声も共有されるようになってきました。治らない病気はたくさんありますが、がんには他の病気とは違う、独特の迫り方があります。
里見 ですから私が告知を始めた頃は、田舎の母親に「お前はなんてひどいことをしているんだ」ってものすごく怒られました。しばらくは完全に少数派でした。ところが、いつの間にか告知するのが「正義」になってしまいました。いまや余命についても、半年だろうが一年だろうが本当のことを言って何が悪い、という具合でしょ? 私はむしろ余命についてはあまり口にしないんですよ。不確実でもあるし。だから、いまや「先生が肺がんの告知を始めたんでしょう。余命についても、なんで本当のことを言わないんですか」と、再び非難される側になった(笑)。有名な論文があって、アメリカでも、まだ1960年代には告知しないことが主流でした。「みんな知りたがっているのに、なぜ告知しないんだ?」と訊かれると、医者は「患者のためだ」と答えていた。それが1970年代後半には告知するのが主流になって、その理由はやはり「患者のためだ」。この間、十五年くらいで、何を正義とするかが百八十度変りました。同じことが日本でも起きたわけです。最近知ったのですが、告知することでやっぱり患者の自殺は増えたそうです。でも、「われわれは失敗した。告知すべきではなかった」なんて声はあがらない。いまではもう「正義」になっているから。
「患者に選ばせる」というのなら
川上 先生は、医療の現場のおかしな点に絶えず疑義を呈されています。例えば、いまでは「患者自身が主体性を持って病気をサバイブしていこう」という風潮になった。だから医師が「治療の選択肢はA、B、C、Dとあります。どれがいいですか?」なんて訊く。患者はCを選んで、その治療がうまくいかなかった時、自分自身を責めるしかなくなる。それはおかしいだろう。「おれはあんたのことを全部診て、Aがいいと判断しているんだ。責任はおれが取る」と言う医者がなぜいないんだ、ともお書きでしたね。先生のこの言葉には本当に胸打たれました。
里見 治療の選択肢を挙げて患者に選ばせるのは、まだいいと思うんです。問題は、患者がCを選んで、うまくいかなかった時、「おれはAが良いと思ってたし、そう言ったよね? だけど、あんたがCを選んだんだからな」という責任逃れをするのは絶対に良くない。少なくとも「自分は患者が選んだCに同意して、その治療をした当事者であり、共犯だ」と思って、次の策を練らなくちゃいけない。

川上未映子(かわかみ・みえこ)
『黄色い家』で読売文学賞、『夏物語』で毎日出版文化賞など受賞多数。他にも連作集『春のこわいもの』、村上春樹との共著『みみずくは黄昏に飛びたつ』など。40言語以上で読まれており、世界で最も新作が待たれる作家のひとり。
川上 治療法といえば、がんの場合は手術をするか、切らずに放射線治療などを選ぶか、という選択があります。食道がんになった当事者が書いた本を読んだことがあって、その著者は名医とされているある医師から「手術しかない」と言われましたが、自分で情報を集めて精査し、転院して放射線治療を選んだ。治療後、その著者が「あなたはなぜ放射線治療の選択肢を挙げてくれなかったのか」と前の病院の外科医を問い詰めたら、医師は顔色ひとつ変えずに「私たちはがんしか見ないんですよ」と。つまり術後のQOLも関係ないし、八十歳、九十歳の人でも「がんを取りたい」と言うなら、私たちは手術を第一選択にします、と答えたというんです。
里見 一方で外科医としては、そういう先生は数もこなしていて、自信もあるし、腕はいいんでしょうね。手術が上手いから確かに術後のQOLも高いのかもしれない。
川上 里見先生が同じ立場なら手術してもらいますか?
里見 それは腫瘍のタイプによりますね。基本的には、食道がんになったら放射線治療を選ぶかな。肺がんなら、たぶん手術を選ぶと思う。今だったらあいつかこいつに執刀してもらおう、あと、彼も上手かったんだけど最近老眼でものが二つに見えると言ってたな、とか(笑)。
川上 そこまでの選択ができるのは医学業界にいる特権ですよね。一般人はどうしたらいいんでしょうか? いわば出たとこ勝負で、受診した病院に任せる、というのが患者の倫理でしょうか?
里見 アメリカではコンシェルジュドクターというのが非常に流行っているそうです。これは一種のかかりつけ医なんですが、すごい金を払って契約して、いざ病気になると、そのドクターの専門の病気でなくても、コネで便宜を図っていろんな医療機関に送りこむ、という形なんです。そのうち日本でも流行るでしょう。本当は家の近くで、あまり金のかからない、顔も広くて腕のいいかかりつけ医を持つことが一番なんですけどね。
川上 母もそうでしたが、世の中、主体性をもって自分の人生の色んなことを決めていたり、自分のことをケアできる人ばかりではありませんよね。みんながみんな、「あの病院にいい先生がいる」とか「手術より放射線がいいみたい」とか情報を集めて、どんな治療を受けるかも自分で決断して――みたいなサバイブができるわけではない。そういう患者には「治療はAでいこう。責任はおれが取るから」と言ってくれるお医者さんがいたらいいのですが……。
里見 桂米朝師匠の小噺ですが、「この薬はドイツからわざわざ取り寄せた貴重なもので、よぉ効く。よぉ効くけども、量を間違えると大変なことになるから、よくよく注意せんといかん。小匙いっぱいだけ、きっちり計って、朝昼晩、決めた時間ぴったりに飲んでたら、こんな病気、すぐに治る! ただし、くれぐれも量を間違えなさんなや」「へへえー」と医者を信用して、うどん粉を有難がって飲んでると、それで病気が治る場合が(笑)。それは冗談にしても、まあ、やっぱり医者を信用しないとね。
世の中に「絶対」はないけれど
川上 告知を受けた患者が、どんなお医者さんを信用するかといえば、先生がアドバイザリーを務めたドラマ(平成版)「白い巨塔」にこんな場面がありました。唐沢寿明さん扮する外科医の財前五郎が「治せないかもしれない、なんて言う医者に、自分の命を預ける患者がいるのか」、「絶対に大丈夫という一言が患者を納得させるんだ」という名セリフを吐きます。先生の『死にゆく患者と、どう話すか』(医学書院)には、このセリフをめぐって看護の学生たちに議論をさせる章がありましたね。がん患者の家族としては、「絶対に大丈夫」と言ってもらいたいです。
里見 私のゼミの子たちに「絶対に大丈夫、って言っていいかどうか」と議論させたら、見事に二つに分かれました。つまり、「世の中に絶対なんてないんだから」――。
川上 そんなことはわかってるけど、言ってほしいんですよ(笑)。
里見 で、一方は、「『絶対に大丈夫』と言ってほしいのだから、言ってあげるべきだ」と。片方は理屈で言って、もう片方は情念で言っているわけだから、妥協のしようがありませんでした。
川上 患者も患者の家族もみんな、手術の前には「絶対に大丈夫」って言ってもらいたいと思うなあ。絶対という言葉が無責任なら「世の中に絶対はないから絶対という言葉は理念として使いませんが、まあ、大丈夫でしょう」と明るめの感じで言ってほしい(笑)。
里見 でも、実際問題として、「絶対」はない。アメリカで作られた、患者とのコミュニケーションについての教育ビデオがあって、その中で、二年前によその病院で乳がんの手術をした女性が骨に転移してやってきた。「転移です、再発です」と告げたら、患者が「『悪いところは全部取った』と言われ、おまけに『念のために』と抗がん剤も半年やらされて、『完全に治った』とも言われたんだ、それがなんで今更」と怒り狂うんです。私自身、自分が診た患者から「前の医者から『治った』と言われたのに話が違うじゃないか」と詰め寄られた経験は何十回とあります。
川上 何か見落としがあったんじゃないか、判断が甘かったんじゃないか、って思うんでしょうね。戸惑いが怒りになって……。
里見 いま目の前にいる医者も含めて、医者全体に怒っているのでしょうね。医者としては、「前の先生の言ったことも噓じゃないんだ、けれど百パーセント本当ということでもない、がんというのはそういう病気なんだ」――そこを分かってもらえないと、次に進めないんです。アメリカ人は「Never Say Never」という言葉をよく使いますね。断定してはいけない。例外は常にあるから。だけど人間は「かもしれない」不確実な状況にはなかなか耐えられない。
川上 もうひとつ、『死にゆく患者と、どう話すか』で、「『手術をすると七割は治る、でも三割は再発してしまう』として、そのリスクを説明するかどうか」という議論も学生たちにさせていました。これにも私は答えが出せないでいます。がんが再発していないかの検査を受けるなんて、本当に生きた心地もしないで病院へ行くわけですよ。でも、三割の再発可能性があると知っておくと、一日一日を大切に生きていこうという心構えを持てるかもしれません。
里見 がんノイローゼの人はたくさんいますが、一番ひどいのは実際に一度がんに罹ったことがある人のノイローゼです。ちょっとお腹が痛い、ちょっと咳が続くというだけで、がんじゃないかと深く悩んでしまう。だから三割ある、あるいは三割しかない再発可能性を告げるべきかどうか――。これには正解はありません。私だったら「まあリスクはないとも断言できないから、外来に通って、たまには検査させてくださいよ」くらいは言うかな。でも、ゼミのある学生が気づいたんですよ。「九割は大丈夫だから」と言っても、糖尿病の患者とがんの患者は違うんだと。糖尿の患者は「おれは医者の言うことを聞いて節制しているから大丈夫だ。一割に入るのは、どうせ酒も飲んで、甘いものも食べてるやつらだろう」と楽観的に思える。そこへ行くと、がん患者は「誰がその一割になるかわからない」と思うからとても怖い。
川上 がんは普段の行いとは、ほとんど関係がないですからね。
里見 そう、誰が再発するのか、誰がなるのか、わからない。まあタバコを吸っていたらプラスアルファで、なりやすくはなるでしょうが、何も悪いことをしていないのに、なる人はなっちゃいます。カルヴァン派みたいになりますが、がんになるかどうかの運命は生まれる前から決められているようなところがありますから。
「間に合わない」と思いつつも
川上 いつまで、どんなふうに抗がん剤を使い続けるのか、という問題もあります。
里見 患者が末期で見込みがなくなっても、ご家族は「何でもやってください」と言い、医者も「では、どうせ効かないけどやりましょう」となる。治療しないで置いておいても仕方ないし、収益も上がらない。副作用で苦しむのは自分ではない。世の中、「何もしないよりはやったほうがいい」と思い込む人は多くて、マスコミもそれを煽りますからね。時間かけて説得するより、やってしまった方が手間もかからない。
川上 それは医療費とも関連してきますよね。先生は、このまま高額医療を野放しにしていくと、いまの医療システムは崩壊してしまうという危機感から、「SATOMI臨床研究プロジェクト(SCP)」という社団法人を設立されています。ホームページを拝見すると「バラ色の未来のためではなく 暗黒の未来にしないために」とありました。先生の主張をシンプルに言えば、医療制度が財政的に崩壊する前に医療費の無駄遣いをなくそう、ということですよね?
里見 そうです。本来、「人間は何のために生きるのか」とか「自分はどんなふうに死にたいのか」などということは、金銭的なこととは全然違う話として、きちんと考えなければいけなかった。残念ながら、それをしてこないまま、日本に金がなくなってきて、いまようやく、みんな嫌々考えざるを得なくなったけど、なにせ嫌々だから、随分と乱暴な話になる。「終末期治療は全額自己負担しろ」と主張する政党が出てきたり、「高齢者は集団自決しろ」なんて「暴言」が本質と関係なく出てきて騒ぎになったりするのも、その一環でしょう。SCPでやっている臨床研究の目的は、余計な薬の投与など過剰医療はやめて、治療を適正化しようということです。その過程で無駄なコストも省ける。薬はどんどん高くなっていて、よく効く薬も大して効かない薬も、非常に高価です。もうすぐ出る子供の筋ジストロフィー症の薬は四億円超だそうですが、こちらは効くらしい。小児科の先生はみんな悩んでいますが――。
川上 子供にはやるべきだと思います。
里見 まったくそう、子供たちのために遠慮することはない。一方で八十歳、九十歳の人を、半年か一年延命させるために何百万、何千万円と使い続けるのか、それはなんのためなのか、ということを真剣に考えないといけない。また、高い薬を製薬会社が言う量より少なく使っても、効果は変わらないだろうという例も数多くあります。ただそれはデータで実証していかないといけない。そんな使用制限や優先順位を考えて、治療を適正化し、コストを削減するための臨床研究なんて、誰一人として余分に治すわけではないから、とても地味な活動です。でも、いまのままでは、どんなにものすごい治療ができたとしても、ビル・ゲイツとイーロン・マスクしか受けられないような世の中になりかねません。
川上 少し下火になった言葉で言えば、「持続可能性」のある医療制度にしたいということですね。
里見 欧米では医療費のコストも副作用の中に入れています。だから、私たちの研究も副作用を抑えるためだし、何より、いま川上さんが言ってくれたように医療制度を持続可能性のあるものにするためでもあります。お前はなぜ自分の専門領域でそんなことをやるのか、よそにも医療の無駄は多いじゃないかとも言われますが、私は自分の専門である肺がんの治療なら無駄なものがある程度見当がつく。でも、他のがんや、高血圧や心臓病や糖尿病やアレルギーなどの治療の無駄は、やはりそれぞれの専門家じゃないとわからない。彼らにも声をあげてほしいのですが、なかなか広がりませんね。
川上 それぞれの専門家の方たちも、医療経済がどれだけ危険水域にあるかなんて説明されたらすぐわかることですよね。それでも腰をあげないのは、「少しでも延命したい」という患者の声もあるのでしょうが、「お金を儲けたい」みたいな欲のせいですか。
里見 お金よりも出世がしたいからでしょうね。新しい薬をばんばん使って成績をあげて論文を書いた方が医者は出世します。製薬会社の金でビジネスクラスに乗って海外の学会へ行ったらコネクションも広がりますしね。私も昔やったことだから、よくわかる(笑)。
川上 だから、「わざわざおれが言わなくてもいいか」みたいになっちゃう。
里見 ちょっと前に、横浜の病院で一緒に肺がんの告知を始めた昔の上司が電話をかけてきて、「やめとけ」と忠告してくれました。「どうせ、いまの医療制度は潰れるんだから、そして潰れたらみんなも目がさめるんだから。わざわざ他人に嫌がられることを言ってもお前が損するだけだぞ」って。でね、私だって内心は「たぶん、間に合わねえよなあ」と思ってます。臨床研究をして、ひとつの薬の費用を適正化していっても、年間で節約できるのはせいぜい百億か二百億円です。五兆円減税をして、その減収は国債発行で賄え、なんていう主張が世論の支持を集めている時に、そんな研究をしていても、もはや医療制度の崩壊は防ぎきれないと思う。
川上 でも、先生は続けるんですよね?
里見 蟷螂の斧もいいところですけどね。でも、近い将来に――例えば私たちの目の黒いうちに――中東に平和が来るとは誰も信じていないけれど、ではすべての和平交渉や平和活動は無意味なのかというと、そうではないでしょう? それと同じことですよ。
その時、どんな言葉をかけられるか
川上 最後にもう一度、余命の話を伺わせてください。先ほど、先生は「余命についてはあまり口にしない」と仰いました。私は何人かの医師から「お母さんに余命を言った方がいい」と言われて、「余命を言うことは患者にとって何のメリットがありますか」と訊いたら、「自分はこれから良くなるんだと希望を持ち、周囲からもそう励まされているのに、病状が進んで身体がどんどんしんどくなる。そのギャップに耐えられなくなるんだ」と言われました。それでも絶対に「残されたのはこれくらい」とは母に言いたくありませんでした。けれどそのうちに母は抗がん剤が効かなくなって、転移も見つかった。その時、私はあるお医者さんに「これから先の治療に正解はありません」と言われたんです。「でも確かなのは、この先はとにかくお母さんができるだけ気分良く、楽しく過ごせる時間を増やしてあげることだと思います」と。
里見 そう言ってくれるのは、いい先生ですね。
川上 本当に感謝しています。それで緩和ケアに移ることになって、手続き上、どうしても母に余命を告げざるをえなくなりました。でも結局、緩和ケアに移るまえに亡くなりました。今でも伝えてよかったのかどうか、怖くなかったかな、と毎日考えますし、夢にも見ます。そのことを先日、養老孟司先生との対談で言ったら、養老先生は余命なんて言う必要はない、いよいよどうしようもなくなったら、そのときに、「やっぱりダメかもしれないね、と言えばいい」と仰ったんです。私、「えっ!」って驚いて、笑ってしまって。粘って粘って「やっぱりダメかもしれないね」って(笑)。でも「はよ言ってや!」と母は笑ってくれたかもしれません。母も私たち姉弟も大阪の人間だから、唯一の救いは、どんなに苦しい場面でも、ユーモアがあったことでした。余命を告げられても、母はプロテスタントの信者だったおかげもあってか、最後までしなやかでいてくれて、「みえちゃん、これが信仰の力やで!」と笑ってみせたし、私が驚かせようと、帯付きの百万円を「退院したら、これで好きなもの買うんやで!」って渡したら、ものすごくウケて受け取ってくれました。「人間、なんだかんだ簡単に死ねへんで、まだまだ働いてもらわな」みたいなことも大阪弁なら言えるし、相手も冗談で返してくるわけです。そんなことを言い合って、泣き笑いすることで少しは救われていたと思います。でも友人たちに聞くと、こんな会話って東京のマジメな家庭だとありえないらしいんですね。先生なら、どんな言葉をかけてあげますか?
里見 立川志の輔師匠が「一番簡単なのは相手を怒らせることで、その次が泣かせること。一番難しいのが笑わせることだ」と言っています。私はなかなかうまく笑わせるまではできないし、それこそ東京では下手に笑わそうとしてスベると惨憺たることになる。なので我ながらクサい言葉だとは思うのですが、こんなことを言ってます――いま、あなたの今後の経過に僕もまったく見通しが持てずにいます。だから、これから何らかの治療をしていくにあたって、僕はあなたの病状に良くも悪くも見通しを持って、上から眺めながら、「こっちへ行けばいい、あっちは危ない」と指図できるわけではありません。真っ暗な道を、あなたと僕が手をつないで、ただ手さぐり、足さぐりで進んでいくだけです。先が見えない状況が続きますが、それでも一緒に歩いていきましょう。
川上 ……もう、そんな言われたら泣きですわ。誰がそんなこと言うてくれはりますか。「ありがとう」しかなくなります。本当のことを告げるだけではなく、ただのきれいな言葉で患者におもねるのでもなくて、あなたは独りじゃない、あなたを独りにしない、と伝える強い言葉ですね。
里見 さっき話に出た患者とのコミュニケーションについての教育ビデオで、出てくるカナダの先生が、これから緩和ケアに行って、抗がん剤などの治療は止めるという患者に、そうなっても「You are still my patient. I am still your doctor.」と言っていました。緩和ケアには緩和ケアで医者がたくさんいるだろうけど、これからも私はあなたの担当医のままなんだよ、と。ほとんど口説き文句みたいだなと思いますが、そこまで言わないと、「先生に見放されたくないから、新しい抗がん剤でも何でもやってくれ」という話にやっぱりなるでしょうしね。
川上 いまの若い医師たちも、やがて、そんな言葉を言えるようになるのでしょうか?
里見 いまはそういう医師を育てないシステムになっていますからね。どこかの部長や教授は私の一つ下の世代でしょうが、そんなことを教えていたら病院や教室の運営なんかできないでしょう。私が若い頃、特に救命センターにいた時なんて、本当にひっぱたかれ、どやされながら修業してきた。そうして「医者」になっていった。あんな人権蹂躙がいま許されるわけがない(笑)。だけどあの先生たちは、「自分たちと同じ仕事をやる奴らを育てる」つもりでシゴいてくださったのだと思います。これから先の医者は、私らと「同じ仕事」であるかどうか、私にはわからない。だから正直、何をどう「教えたらいい」のか、見当がつかない。
川上 先生は新書の中で、「『俺たちの頃』は、辛かった。『近頃の若い者』がそれを追体験する必要なんか、ないのだろう。だがだからと言ってべつに俺たちは、やり直したいなんて思わない。それはどうしてだろうか」と書いていましたね。打たれました。ほかにも、ふと顔をあげて胸を押さえたくなる文章が、たくさんありました。必読の書だと思います。
里見 これからも、例えば膵臓がんの手術でも白内障の手術でも、特殊領域の名人芸を極める医者は出てくると思います。だけど医者はそういう技術職に徹するだけでいいのだろうか。「最期を看取る」のは、すべての医者の仕事なのか、特殊な専門領域の医者だけの仕事なのか、ナースの方がいいのか、それともAIやロボットに任せるべきなのか。世の中が何を「医者」に望むのか、じゃないですかね。
(かわかみ・みえこ 作家)
(さとみ・せいいち 医師)
最新の対談・鼎談
-
2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念
階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない
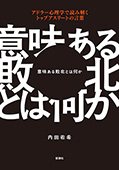
意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―
-
2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談
ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―
-
2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談
私たちの中に生きている三島
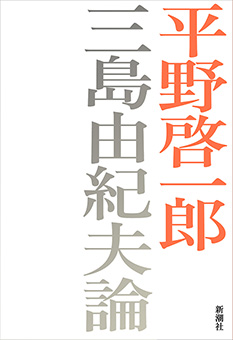
三島由紀夫論
-
2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談
池上さんと村上さんが話す前に考えていること
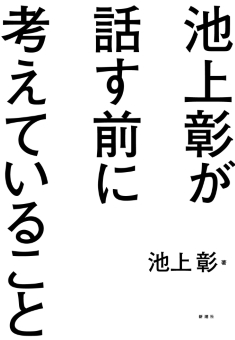
池上彰が話す前に考えていること




