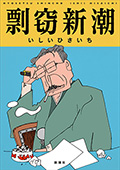書評
2025年9月号掲載
石川直樹『最後の山』刊行記念特集
青春の残り香
対象書籍名:『最後の山』
対象著者:石川直樹
対象書籍ISBN:978-4-10-353692-5
世界には八千メートルを超える山が十四ある。
その山のすべてに登るということが、登山の歴史において何らかの意味を持つという時期はすでに過ぎている。
世界で初めてその十四座に登ったのはイタリアのラインホルト・メスナー、女性で最初に登り切ったのはスペインのエドゥルネ・パサバン、日本で最初の十四座サミッターになったのは竹内洋岳、という具合だ。
だから、当然のことながら、石川直樹が八千メートル峰のすべてに登ろうと思い決めたのも、なんらかの記録のためではなかった。
エベレスト、マナスル、ローツェ、マカルー、ガッシャブルムII峰、ダウラギリ、カンチェンジュンガ、K2、ブロードピーク、二度目のマナスルと登っていくうちに、十四座のすべてに登ってみたいという思いが強くなっていったのだという。
その理由として、この『最後の山』においては、二つのことが述べられている。
ひとつは、ヒマラヤ登山において永くサポート役を務めてきたシェルパたちのあいだに、自らのための登山をするという新しいムーブメントが生まれ、その主役のひとりであるミンマGという人物と巡り合ったことで、彼らと行動を共にすることへの喜びを覚えるようになったからだという。
もうひとつは、GPSやドローンなどの精度が上がることにより、これまで頂上と思われていた地点とは別の頂上が出現するようになって、その「真の頂」というものへの強い関心が生まれたからであるという。
しかし、私には、そうした理由以上に、すべきことは自らが見つけなければならないフリーランサーの石川にとって、それが久しぶりに心を熱くさせてくれる「すべきこと」と映ったのではないかと思えてならない。すべきことが現れて、気持が高ぶった。
その高ぶりに身を任せた石川は、アンナプルナ、ナンガパルバット、ガッシャブルムI峰、チョオユーと、一年で一気に四座に登り、ついにはシシャパンマを残すだけになる。
だが、このシシャパンマが、石川にとっては難峰となる。
頂上にあと二百メートルと近づきながら、ヒマラヤの登山史の中でも、そう多くない悲劇的な連続遭難を眼前にすることとなり、撤退を余儀なくされる。
それでも、その翌年、ふたたび、彼にとっての「最後の山」であるシシャパンマに向かうことになる……。
石川は、年齢的には四十代の半ばを過ぎているし、すでに多くの著作を持っている。しかし、この『最後の山』には、一人称に「ぼく」が使われているからというだけが理由ではない、不思議な初々しさがある。青春の残り香のようなものが漂っている気がするのだ。
何故か。
それは、その底に自分は何者なのかという問いを秘めているからだと思われる。
自分は登山家なのか。いや、違う。少なくとも、山野井泰史のような尖鋭なアルパイン・クライマーではない。
冒険家なのか。たぶん、違う。未知の土地や新しい体験を求めてはいるが、そのために人生のすべてを費やして突き進んでいるわけではない。
紀行作家なのか。結果として何冊かの本は出しているが、書くために旅をしたり、山に登ったりしているわけではない。
写真家なのか。確かに、常に撮る者でありつづけているが、そう言い切れるかどうか、わからない……。
そうした思いの揺らぎのようなものが、次々と八千メートル峰を登らせながら、自らを確固たる存在として描くことをためらわせている。
もちろん、それは欠点ではなく、私にはむしろ美質であると感じられてならない。
自らを過剰に誇らないだけでなく、ミンマG以外にも、ザイル・パートナーとしてのシェルパたちを、友人として柔らかな筆遣いで描くことができているのもそうしたところからなのだろうと思われるからだ。
しかし。
十四の八千メートル峰の「真の頂」に立ったいま、石川にひとつの覚悟に近いものが生まれたように思われる。
《ヒマラヤでの経験は決して折れることのない太く頑丈な杖のようなもので、それを片手にぼくは歩き続ける。その杖を頼りに、願わくは死ぬまでずっと歩き続けたいと思っている》
それがどこに続く道かわからないまま、石川直樹は前に進んでいくことになるのだろう。杖を持った手と反対の手には、やはりカメラを握りつつ。
(さわき・こうたろう 作家)