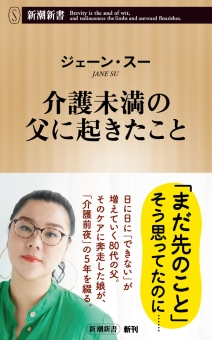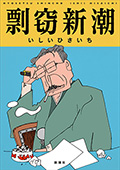書評
2025年9月号掲載
介護が人生の予習であるならば
ジェーン・スー『介護未満の父に起きたこと』(新潮新書)
対象書籍名:『介護未満の父に起きたこと』
対象著者:ジェーン・スー
対象書籍ISBN:978-4-10-611098-6
義父母の介護が始まって、そろそろ六年になる。この日がはっきりとしたスタートではないか? と考えているのが、義父が脳梗塞で病院に運ばれた2019年8月下旬のことで、同じ日、義母はショックのあまり、義父の身に何が起きたのか、自分がどこにいるのかさえわからなくなるほど茫然自失となり、その後しばらくして、レビー小体型認知症と診断された。義父は幸運なことにほとんど後遺症も残らず回復したが、義母は日を追うごとに症状が進み、今現在は介助なしで暮らすことはできないほど重度の状態になっている。
義父は九十歳を超え、元気ではあるが、もの忘れの症状も出始めた。老老介護による在宅での暮らしは限界を超えている。介護保険を限界まで使ってサービスを受けても夫婦の暮らしは成り立たず、自己負担による介護費用は毎月驚くほどの金額になっている。
老人ホームに入ればいいんじゃないですか? と思う人が多いだろう。もちろん、私もそう思う。しかし問題はそこまで単純ではない。義母が入所できる施設には、介護度の違う義父は入所できない。夫婦は常に一緒にいなければならないと固く信じている義父が義母と離れることを拒み、頑ななまでに首を縦に振らない。昭和、平成、令和を生き抜いてきたスーパーマンみたいな彼を怒らせると、大変なことになる。デイサービスは週に五日、ヘルパーによるサービスも週に五日、訪問看護師の訪問は週に一度、そして私と夫による週末の介護で、なんとか在宅介護が継続されている。ときどき、「なぜお嫁さん(私のこと)が完全同居して介護してあげないのですか?」と聞かれることがある。可能な限り冷静に返すが、心中穏やかではない。令和に“嫁”という概念があっていいのか。私にはフルタイムの仕事があるじゃないか。
そして私はいつも考える。実の親の介護と義理の親の介護、どちらが大変なのだろうか? 私の実の両親はすでに他界しているので、実際には二人を介護することは不可能なのだが、もしそんなことになったとしたら?
ジェーン・スーの『介護未満の父に起きたこと』を読んだ今は、「うーん、どっちもきつい!」と思う。しかしそう思いながらも、あろうことか私は、年老いた実の親の手を引く自分を想像して、心に小さな灯りがともる。涙が浮かんできたりする。あの手この手で父の生活を支える著者の奮闘を想像するたびに、大変なのは重々承知で、二人を応援したくなってしまう。
それでももちろん、父のサポートは一筋縄ではいかない。現代のツールを駆使して父のためにと考えることも(それもめちゃくちゃ考える)、きままな父はあっさりとひっくり返す。家事代行サービスのスタッフとのトラブル、コロナ、転倒、なぜだかちらつく女の影……。次から次へと父が巻き起こすトラブルは娘を悩ませるわけだが、そこに不器用な父と娘の互いへの愛情が透けて見える。こんなことを書いたら著者には「そんなやつじゃねえから!」とお𠮟りを受けるかもしれないが。
本書は実の娘による父のケアの記録というよりも、著者の人生にとうとうやってきた、自分の未来との対峙の物語のように思える。昔から破天荒で迷惑をかけられっぱなしだったけれど、どうしたって嫌いにはなれない父には、末永く好きなように暮らしてほしいと願う著者の挑戦はつまり、自分の将来をも見つめることなのだ。著者は父の生き方の向こうに、自らの人生を重ねているはずだ。
介護って、人生の予習みたいなものだと思う。誰だって、必ず老いていく。どれだけ今は元気でも、どれだけ働くことができていても、自分ひとりでやれていたことも、誰かにお願いしなくてはならない未来は必ずやってくる。
それでも希望はある。四十代後半から介護を経験した我々が、その悔しさも、悲しさも、情けなさも、金も、愛も、死も、全部書き切って、マニュアルとして残していけばいいのだ。妙に口が達者で、ついでに文章が書ける人間たちが後期高齢者となるまでに、何冊も書き上げておけばいい。
そうすれば、「どうもあそこのババアが始まったみたいだな」「それならプランA『地域包括支援センター』だ」とか、「三丁目のジジイの手足が妙に細いぞ」「よっしゃ、プリンで摂取カロリーを無駄に上げに行こうぜ」とか、そんなことができる未来はたぶん来る。本書はそんな未来のマニュアルの一冊になるはずだ。
(むらい・りこ 作家)