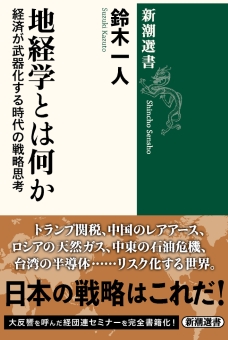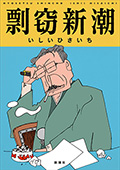書評
2025年10月号掲載
【小泉 悠書評二本立て】 今月の新潮選書
「ラスボス」が語る地経学入門
鈴木一人『地経学とは何か─経済が武器化する時代の戦略思考─』(新潮選書)
対象書籍名:『地経学とは何か─経済が武器化する時代の戦略思考─』
対象著者:鈴木一人
対象書籍ISBN:978-4-10-603934-8
地経学という言葉を頻繁に目にするようになったのはいつ頃からだろうか。私の場合、「オッ、地政学かと思ったら違うのか。地経学なんていう言葉があるのか」というようなことを数年前に思った記憶があるので、おそらく横文字ではなく日本語で遭遇したのだろう。とすると、2020年代に入る頃には、もうこの概念が日本語になって言論空間で流通していたことになる。
そうこうするうちに2022年には地経学研究所(IOG)が設立されて、我が国における外交・安全保障議論の中心に「地経学」がドーンと鎮座しているということになった。本書『地経学とは何か─経済が武器化する時代の戦略思考─』の著者である鈴木一人教授は、まさにそのIOGの所長を務める人物である。ということは、日本における地経学議論のラスボスみたいな存在だ。そのラスボスが地経学について語る本書は、入門編として最適の一冊と言えよう。
しかし、地経学ブームの少し前には地政学がブームであったことを、多くの読者は覚えておられるのではないだろうか。それから経済安全保障ということが盛んに叫ばれるようになり、今度は地経学だということになった。一応、安全保障を商売としている私から見てさえ、実に目まぐるしい。一般人からすると「なにそれ」という感じであろう。
そこで改めて整理してみたい。地政学、経済安全保障、地経学。これらの諸概念はいかなる関係にあるのだろうか。まずは字面が似ている地政学(Geopolitics)と地経学(Geoeconomics)から手をつけてみよう。
地経学という用語が地政学を意識して作られたものであることは明らかだ。鈴木教授の言い方を借りるなら、「これまでの「地政学」の枠組みの中に、経済が「武器」として組み込まれ、国家間対立の手段として、経済が用いられるようになる」という関係性であるらしい。経済の地政学化、と理解しておけばよいのだろうか。
では、その地政学とは何なのだ、と言われると、これがまた難しい。当たり障りない感じに言えば「地理と政治の関係を研究する学問」ということになろうし、最も辛辣な評価では「侵略を正当化する疑似科学」であるとされる。平均を取ると、「地理をめぐる国家間のゼロサムゲーム的論理」といったあたりになるだろうか。地政学的理解においては、土地とか資源というのは奪い奪われるものであり、Win-Win的関係は基本的に想定されていないからだ。したがって、地政学的世界観では最終的に強者が弱者を併呑し尽くすまで生存競争が続くとされている。
だが、これはあまりにも「力」中心の世界観だ。皇帝とか将軍とかが血走った目で見ている世界の話であって、算盤片手の商売人的=経済的論理は全く無視されている。
現実に私たちの生活をかなりの程度まで規定している経済の論理は、もうちょっと柔軟だ。なにしろ商売人は譲るということを知っている。値引きや積み増し、つまりは「オマケ」という若干の損失を受け入れることで財を売り、総合的には売り手と買い手の双方にメリットをもたらす。他方、儲からないとなったら、どんな国家の大事であろうと商売人は手を出さないし、逆に儲けを追求して自滅的なことをしたりもする(レーニン曰く、「お前の首をくくるからロープを売れと資本家に言ったら、売るだろう」)。
こうしてみると、地政学と経済の食い合わせはいかにも悪い。「経済安全保障」というのは、この本質的に折り合わない二つの論理を繫ぎ合わせるためのトランスミッションみたいなものではないだろうか、というのが私の理解である。
一方において、経済安全保障は、地政学の論理を経済に持ち込む。「いくら儲かるからってあの国にこの装置を売っちゃダメだぞ」「利益は薄いかもしれないが、これだけは国産できるようにしておけ」といった具合だ。他方、経済安全保障は逆のチャンネルも提供する。「この分野で世界から必要とされるようになりましょう」「規制作りで世界標準をリードしましょう」……など。こうして地政学の論理と経済の論理に渡りをつける道筋が存在したからこそ、地経学なる考え方が成立し得たのだろう。
問題は、両者がぎこちなくでも互いに手を携えなければならなくなった背景であろう。経済・産業・情報のグローバル化が進み、かといって国家間の対立もまた激化しているというのが我々の暮らす2025年の状況である。地政学も経済も、それぞれの論理を完全に押し通すということはなかなかできない。つまり、地経学は「地政学化した経済」であると同時に、「経済化した地政学」なのでもあって、地経学の時代は当面続いていくのではないかと思われる。
そうした時代における複雑な状況を描いたスケッチ集のようにしても、本書は読めそうである。
(こいずみ・ゆう 東京大学先端科学技術研究センター准教授)