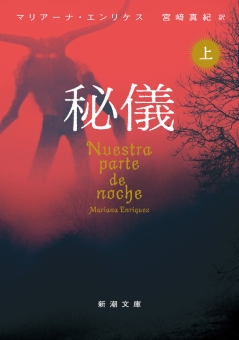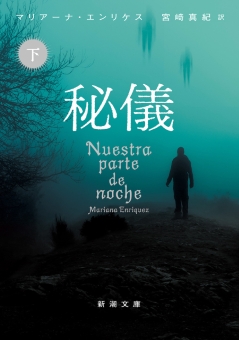書評
2025年10月号掲載
今月の新潮文庫
ホラーだからこそ描ける世界のありよう
対象書籍名:『秘儀』(上・下)
対象著者:マリアーナ・エンリケス、宮崎真紀 訳
対象書籍ISBN:978-4-10-241061-5/978-4-10-241062-2
世界的に評価されている“アルゼンチンのホラー・プリンセス”ことマリアーナ・エンリケス。日本でも初の邦訳短編集『わたしたちが火の中で失くしたもの』が注目され、続く『寝煙草の危険』はホラー小説のランキング本『このホラーがすごい! 2024年版』では海外部門首位に輝く快挙をなしとげた。
その作風はダークで残酷で幻想的。幽霊・死者・廃墟などホラーでおなじみの題材を用いながら、決して狭い世界に閉じこもるのではなく、貧困やドラッグなどアルゼンチン社会の暗部をも、現代の恐怖として描き出す。ラテンアメリカ文学には超自然的要素を取り入れることで、リアリズムを超越したリアルを描写するマジックリアリズムの伝統があるが、ホラーの帝王スティーヴン・キングの影響を強く受けたエンリケスの文学は“ホラーリアリズム”とでも呼べるだろうか。
『秘儀』はエンリケスが2019年に上梓し、数々の文学賞を受賞した長編だが、日本で彼女の長編が紹介されるのはこれが初となる。ゴシックな美意識と幻想性が際立っていた二冊の短編集と共通する特徴は当然あるものの、邦訳で一一〇〇ページを超える本書は、より骨太重厚にして多声的。世界を丸ごと物語に包含しようという意図すら感じられるメガノベルだ。
物語を一言で表現するなら、血と魔術に彩られた家族の年代記である。並外れた霊媒であるフアンと息子ガスパルの屈折した父子関係が、二人の人生に暗い影を落とす〈教団〉の存在を交えながら綴られる。フアンは〈闇〉を召喚できる力を備えており、教団幹部はその役割をガスパルにも受け継がせようとするが、フアンは息子を〈教団〉から遠ざける。ガスパルにはそんな父の真意が伝わらない。
物語は視点の異なる六章からなり、第一章ではフアンが事故に巻き込まれた妻ロサリオの死に疑念を抱きながら、年一度の儀式に参加するため〈教団〉の本拠地を訪れる。鉤爪のある〈闇〉が顕現するおぞましい儀式の場面は魔術ホラーとしても出色で、本書のひとつの読みどころだ。第二章ではフアンの主治医の立場から〈教団〉と〈闇〉についてより深く語られる。第三章はブエノスアイレスで父と暮らすガスパルの物語。霊感を備えたガスパルと親しい友人たちとの賑やかな日々を、死と恐怖に染め上げられたエピソードとともに描くこの章は、なるほど作者が愛読するスティーヴン・キング風だ。ここまでは1980年代を背景としているが、第四章では1960年代まで時代をさかのぼり、ドラッグとオカルトが流行するロンドンを舞台に、ケンブリッジで学ぶロサリオの青春が描かれる一方、〈教団〉の邪悪な一面がいっそう露わになる。共同墓穴を取材するジャーナリストが無数の死者の存在に気づく短い第五章を挟み、最終章では1980年代から1990年代を舞台に、成長したガスパルが〈教団〉と〈あちら側〉と対峙する姿が描かれる。もちろんこの太い幹からは、無数のエピソードが枝葉のように伸びていて、それぞれが不気味で印象的だ。たとえばガスパルの友人アデラが廃墟に忍び込んで忽然と消えてしまう展開や、無数の人骨が並べられた〈あちら側〉のおぞましい光景は忘れがたい。
ページを捲るうちに湧き上がってくるのは、現代史の深淵を覗きこんでいるという感覚だ。イギリスにルーツを持つ〈教団〉は、奴隷や貧しい子供を犠牲に〈闇〉と接触し、特権階級に富と力をもたらしながら、アルゼンチンを含む各国に根を張った。世界規模での邪悪と残酷を容赦なくえぐった本書は、グローバル時代のゴシック小説とでもいうべき顔を備えている。もっとも〈教団〉の描かれ方は多面的で、フアンを含むメンバーの家族愛や性愛が複雑に絡み合う。単なる悪の結社と呼べないのがまた興味深いところだ。
そして〈教団〉とともに物語に大量の死者を生むのが、戦後アルゼンチンの政治状況である。軍事政権によって多くの市民が投獄・拷問・処刑された恐怖の時代を、エンリケスはこれまでも扱ってきたが、本書はその傾向がかなり強い。あまりにも不条理で恐ろしい現実をフィクションに封じ込めるため、エンリケスはホラーという古くて力強い物語の形式を採用する。今エンリケスが世界中で支持されるのは、彼女の描くダークな物語に、それぞれの国で命や尊厳を奪われた人々の叫びが、確かに描かれているからだろう。ホラーだからこそ描くことができるこの世界のありように、心かき乱され、打ちのめされてほしい。
(あさみや・うんが 書評家)