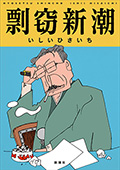書評
2025年11月号掲載
いしいしんじ『チェロ湖』刊行記念特集
三枚の黒い円盤
『チェロ湖』をめぐって
対象書籍名:『チェロ湖』
対象著者:いしいしんじ
対象書籍ISBN:978-4-10-436305-6
はじめに「かたち」が浮かんだ。
三つの黒い円盤が、上、中、下、と宙に浮いている。それぞれが湖で、水面は、同じ向き、反時計まわりに回転をつづけている。上から順に、主人公の時間、主人公の父母の世代の時間、主人公の祖父母の世代の時間をあらわす。
主人公は、自分の時間の湖に小舟をだし、まわりつづける水面のまんなかで釣り糸をたらす。糸の先には、まっすぐな蓄音器用のレコード針が結びつけられている。深々とおりてゆく針は、父母の水面へ、さらに祖父母の水面へと沈み、その時代、その水辺に響いていた「ものがたり」を釣りあげる。
書き出しでもストーリーでもなく、いきなり小説ぜんたいの「かたち」が明確にみえるのはこれがはじめてだった。蓄音器は、2009年に音楽の師匠に勧められて購入し、自宅でメインのオーディオ装置として日常でつかっていた。また、ほぼ同じ時期に地元の先輩に誘われ、早朝の琵琶湖でのコアユ釣りにもなじんでいた。「釣り」と「音楽」、ひいては「ものがたり」が、「針」というありふれたものでつながれる。
こうした「かたち」が、ぼくは、とても自然だと感じた。この「かたち」を踏まえてさえいれば、どんな「ものがたり」が釣れようが、不自然なことにはならない、とも思った。
「新潮」での連載はとてもおだやかにはじまった。タイトルは「琵琶」湖にちなんで、同じ弦楽器の「チェロ」湖とした。
ものがたりの釣り針は、1920年代から2020年代のあいだをランダムに行き来する。湖周をまわりつづける野生の馬たち。風に乗って響きわたる楽器の音。岸辺に流れつく無数の耳たぶ。下卑たようでいて清廉な精神をもちあわせる湖岸のひとびと。
乗馬、旅、建築、音楽にお茶。日常の暮らしで触れたことが、小説にはいりこんだかと思うと、小説に書いたことが、日々の暮らしにこつぜんと現れた。小説を生きているのか日常を書いているのか、その境界があいまいになっていった。三枚の円盤は、日常の暮らし、小説の表面、さらにその奥底をあらわしているようにも感じた。ぼく自身、不透明な湖のただなかで、深さのわからないことばにむかって釣り針をたらしていた。
終盤、湖底にたまった堆積物が、小説のなかに、けしてもとへはもどせない災厄をもたらす。目の前で生じるできごとが、湖岸の暮らしを粉々に壊していくさまを、淡々と書きつづった。ことば以前の「原ものがたり」が、ことばのものがたりをのみこんでいく。そのさまをあらわすのもまた、ことばによってでしかできないのだ。
ぼく自身も「原ものがたり」にのみこまれていた。何度も湖に落ち、堆積物のなかでことばを失った。
なんとか最後までたどりついたのは、はじめに浮かんだ「かたち」が救命ブイのようにはたらいたからかもしれない。三枚の円盤は、いまふりかえれば、書き手、小説、読み手の関係にもみえる。書いているぼくの底と読んでくれる読者の底は、まわりつづける「ものがたり」とまっすぐな釣り針をとおし、時と場所をこえて響きあうことができる。
読者には、小説をこの「かたち」のまま、まるまる引き渡したい、という感覚が、ぼくの水底から湧きあがった。もとのままの文章はほとんど残っていないほど、ゲラ全体に朱を入れた。分量は百ページほど減り、小説ぜんたいの風景は、夏の朝の湖面をみわたすかのように広々とひらけた。
以前とあるインタビューで、これからどんな小説を書きたいですか、と訊ねられたことがある。反射的に、宇宙のなぞに迫りたいです、とこたえたが、書きあがった「チェロ湖」には、迫るとはいかないまでも、そのあたりのことに、わずかに触れた感触はある。
自分、というなぞ。こころの不思議。ひとも魚も鳥も虫も、「ガイライシュ」も、みながみな、ひとしなみにもつ、いのちのミステリー。
さまざまなことがわからないから書きはじめる。いつもそうだし、今回はとくにそうだった。書いているあいだじゅうわからなかった。書きおわったいまも、いったいなんなのかよくわかっていない。
ただ、なにかは釣りあがった。その手ごたえはいつまでも、背景放射のように、深々と残響している。宇宙とは、まわりつづける三枚の円盤のかたちをしているのかもしれない。
(いしいしんじ)