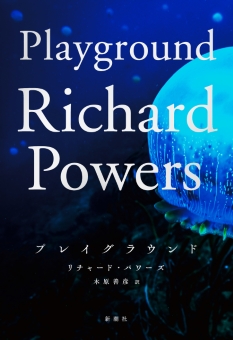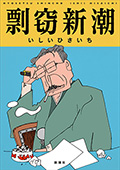書評
2025年11月号掲載
生命はみな遊ぶ
リチャード・パワーズ、木原善彦 訳『プレイグラウンド』
対象書籍名:『プレイグラウンド』
対象著者:リチャード・パワーズ/木原善彦 訳
対象書籍ISBN:978-4-10-505878-4
「海」と「AI」がキーワードの本書のタイトルが、なぜ『プレイグラウンド』なのか。
もちろん、著者のリチャード・パワーズは、答えの一端と思われるものを作中で示唆している。それはおそらく、「リアルであれバーチャルであれ、世界は『遊び場』である」ということだ。
ただし、このシンプルな帰結を「世界は所詮遊び場に過ぎない」とペシミスティックに受け取ると、パワーズの視座からはかえって遠ざかってしまうだろう。この小説は、我々を含むすべての生命が「遊び場」でひたすら戯れているということがたまらなく愛おしくなるような物語なのである。
そもそも、生物にとって「遊び」は余分な暇つぶしではない。人類は古来、子ども時代の遊びを通じて狩りや漁を学び、道具やルールを作り出す訓練をおこなってきた。犬やチンパンジーやイルカはもちろん、昆虫でさえ遊ぶという研究結果も報告されている。本作の重要な舞台である海でエイや魚たちが見せる見事なダンスは、我々の目には遊びと区別がつかない。遊びは常に、生命の本質としての「発見」や「創造」と密接に結びついている。
この物語の主要な四人の登場人物も、一種の「遊び」がシリアスな形で人生とひと続きになってきたような面々だ。まずは、フランス領ポリネシアのマカテア島で暮らす芸術家、イナ・アロイタ。その夫、ラフィ・ヤングはシカゴ育ちの黒人で、かつては文学と詩作に人生を捧げていた。ラフィの高校時代からの親友でコンピュータ・オタクだったトッド・キーンは、世界的な人気を博す仮想空間プラットフォームを開発し、大富豪となっている。
そして、残るもう一人の主人公が、海洋生物学者のカナダ人女性、イーヴリン・ボーリューである。ありきたりな幸福よりも海の一部となるような生き方を選んできたイーヴリンの視点を通じて、「海の魔法」と呼ぶにふさわしい海中世界の豊かさと驚異が色鮮やかに描かれる。
物語は、イナとラフィが暮らすマカテア島に、ある開発計画が持ち上がるところから始まる。島を拠点にして、裕福なリバタリアン(自由至上主義者)たちのための海洋都市を建設するというのだ。島民たちは、このプロジェクトを受け入れるかどうか、選択を迫られる。
島の運命はどうなるのか。かつての強い絆が失われ、深い断絶で分かたれているラフィとトッドの間にはいったい何があったのか。今は島に一人で滞在している老いたイーヴリンは、どんな人生を歩んできたのか。それら三つのストーリーラインを軸に、過去と現在を行き来しながら物語は進んでいく。
私はこの小説を味わっている間じゅう、「海の魔法」と「テクノロジー」のせめぎ合いに心を奪われていた。人間は、「海の魔法」を魔法のままでは終わらせない。海とそこに暮らす生物の営みの原理と法則を突きとめようとする。それが、「科学」である。科学をおこなう者たちは、自然界に敬意と畏怖を抱き、その豊饒をあるがままに保つべきだと考える。
一方、しばしば「科学」とペアをなす「テクノロジー」は、より人間の側に立つ。人々の利便性、安全、娯楽などのために新たなツールを生み出すだけでなく、ときに自然を支配し、破壊する。
だが、トッドが青年時代を通じて体験するコンピュータの目覚ましい発展と、それを支えるオタクたちの情熱には、胸を打つものがある。トッドが作り出す仮想空間プラットフォーム──その名も「プレイグラウンド」は、それと並行して進化するAIと同じく、テクノロジーが進む道中にあるメルクマールとして当然のものと思われる。
悩ましくも興味深いのは、「科学」も「テクノロジー」も、そのもっとも根源的な原動力は経済的利益ではなく、「遊び」と不可分な「好奇心」だということだ。つまり、世界を理解したいというイーヴリンの願いと、世界を創造したいというトッドの欲望は、実は同じ根を持っている。
この物語が活写する人間の愚かさ、哀しさ、そして愛おしさは、おそらくそこに起因するのだろう。そのことを感じ取ったとき、私は「世界は『遊び場』」の意味が初めて理解できた気がした。生命とはすべからく遊ぶものであり、そこにはいい遊びも悪い遊びもないのだ。
最後に付け加えておくと、パワーズが施したある仕掛けによって、この小説もまた遊びの産物となっていることが、物語のラストで明らかになる。その驚きもぜひ堪能していただきたい。
(いよはら・しん 作家)