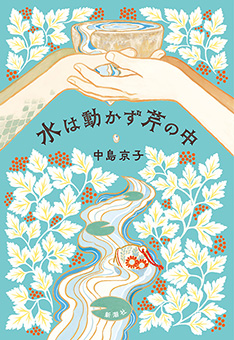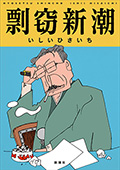書評
2025年11月号掲載
河童の見た「秀吉の朝鮮出兵」
中島京子『水は動かず芹の中』
対象書籍名:『水は動かず芹の中』
対象著者:中島京子
対象書籍ISBN:978-4-10-351352-0
類例のない小説である。これをいったいどうやって読者に紹介したものか正直言って見当がつかない。でも絶対に紹介したいので頑張ってやってみよう。
長いスランプに陥った小説家がやけっぱちになり旅した唐津の山奥で陶芸体験をする。その窯元の夫妻の家に泊めてもらうことになり、おいしいお酒を飲みながら不思議な「水神夜話」を聞く。それがあまりに面白く、長い話の続きが聞きたくて唐津に通うことになる。その「水神夜話」が突拍子もないのだ。
「水神」とは神様ではない。昔生きていた動物ともヒトともちがう存在で、水の中に住み、背中には甲羅、頭には皿、手には水かきがある。つまり「河童」なのだ。もともとインドに住んでいたのが中国に移住し、さらに戦乱を避けて日本にやってきた。熊本の球磨川で平和に暮らしていたのに加藤清正の非道な仕打ちに遭って九州各地に離散していた。
そんな水神ワールドを脅かすニュースが入る。豊臣秀吉が朝鮮と明を征服するために戦を起こすというのだ。戦が起きれば、球磨川の悲劇の再来で、きっと朝鮮や明の水神も巻き添えになってたくさん死ぬ。
かくして水神たちは秀吉の計画を阻止するために立ち上がる──のだが、彼らは笑ってしまうくらい無力。暴力はからっきしで、誰かと戦うなどまったくできない。最大限に頑張って、川を増水させて軍勢が進むのを遅らせるぐらい。
かといって、弁が立つとか交渉力があるわけでもない。なにしろ水神は噓がつけない。いや、つけないわけじゃないが、水神の噓とは冗談として笑える噓であり、人間のように他人を騙して自分の利益を得ようという陰険な噓をつく発想がない。
だからみんなして、オロオロと東奔西走するばかり。ただ、彼らの武器は水中での移動。どうやら魚のように泳げるので佐賀から熊本まで陸の馬なみに移動できる。だから情報伝達力は早い。あちこちに仲間もいる。周囲の環境に合わせて体色を変化させるというカメレオンのような技があり、人間の目には一切見えない。この力を利用して、彼らは大名や著名な茶人などの居室に忍び込むことができる──。
といった調子で、水神の末裔らしき(!)窯元のサワタローさんが先祖から伝わる話をゆるゆると語るのだが、理解いただけるだろうか? 無理? まあ、しかたない。プロの作家であるはずの私も、本作の前では戦争に立ち向かう河童なみに無力である。
しかし私も河童なみに物語世界に溶け込んでその面白さを味わうぐらいはできる。本書は何が凄いと言って、ファンタジックな設定とは裏腹に、「夜話」部分が本格歴史小説であることだ。
秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)は「十六世紀最大の国際戦争」だという。にもかかわらずこれについて詳しく書いた小説は極めて少ない。秀吉や同時代の大名たちを主人公にした小説にはもちろん出て来るが、メインテーマになることは稀だ。なにしろ陰惨で、誰が活躍するわけでもなく、最後は日本側が敗北する。物語として楽しさや救いがなさすぎる。
そんな困難なハードルを「夜話」は軽々と乗り越えてしまう。なにしろ語り手たちは水神(河童)。キャラがかわいくて陰鬱な気分が続かない。四人(四匹?)の水神が主に活躍するが、そのうちの一人は千利休に会って戦を阻止してくれるよう頼む。それは無理だと断られたものの、利休に気に入られ、茶人の名をひっくり返して「休利」という名前をもらう。以後、この水神は「きゅうり」と呼ばれるようになった──なんてリラックス効果絶大な逸話も盛りだくさん。
水神たちは癒やしキャラなだけではなく、機動力と隠密力に優れたレポーターでもある。薩摩の河童は同地を出入りする明人に密着し、唐津の河童の娘は領袖波多氏の妻や朝鮮出身の陶工の娘と親しくなる。最も面白いのはニタと呼ばれる対馬の水神だ。彼は朝鮮語も流暢に操り、「元は河童」という噂のある(!)小西行長にくっついて朝鮮出兵に従軍する。そして水神たちの中にはヒトの噓と残虐さに驚くうちに身に変化が現れるものたちも……。
こうして、四匹の河童の目を通して読者は四百年前の大戦争をまさに国際的視点でリアルに感じることができてしまう。これに最も近い味わいの小説は──これまた信じられないかもしれないが──船戸与一の歴史巨編『満州国演義』や『蝦夷地別件』だろう。船戸さんがバイオレンスの血糊の下で実はリアリズムを貫いているように、中島さんはユーモアの釉薬をかぶせながら歴史的真実を鮮やかに描き出している。
たぶん、この紹介ではさっぱりわからないと思うが、なんだか凄い作品だと想像はつくだろう。そう、あとは読んでいただくしかないのである。
(たかの・ひでゆき ノンフィクション作家)