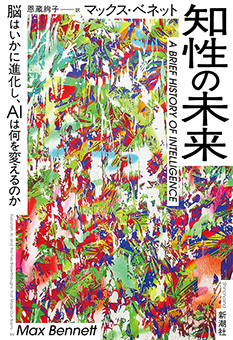書評
2025年12月号掲載
マックス・ベネット『知性の未来』刊行記念特集
世界の見方が変わる知的エンタテインメント
マックス・ベネット、恩蔵絢子 訳『知性の未来─脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか─』
対象書籍名:『知性の未来─脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか─』
対象著者:マックス・ベネット/恩蔵絢子 訳
対象書籍ISBN:978-4-10-356551-2
本書の書評を依頼されたときは、メールを斜め読みして、面白そうだったので「いいですよ」と気軽に返信した。送られてきたゲラは五〇〇ページもあって、正直、ちょっと後悔した。ところが読みはじめるとものすごく面白くて、夢中になって三日で読み終えてしまった。
本書の魅力は、著者のマックス・ベネットが研究者ではなく、AIテクノロジー企業を創業した起業家で、いわば“門外漢”なところにある。現代の研究者は自分の専門分野に閉じこもっていて、それ以外の分野に越境しようとすると、無礼な行為として重箱の隅をつつくような批判をされかねない。そんな偏狭なアカデミズムの世界では、生命の誕生からAIまで、知性の歴史をわずか5つのブレイクスルー(イノベーション)で説明するような大胆な試みはとうていできないだろう。
そうはいっても、ベネットはたんなる素人ではない。AIシステムを人間(消費者)に応用するビジネスをしながら、脳という不可思議な器官に魅了され、本を読むところから始めて多くの神経科学者たちと長文でEメールのやり取りをするようになり、ついにはいくつかの研究論文を発表するまでになった。そうして熟成されたアイデアを、満を持してかたちにしたのが本書だ。
知性を生み出した5つのブレイクスルーはどれも興味深いが、ここでは神経系(ニューロン)をもつ原始的な生き物である線虫を見てみよう。
わたしたちが知る動物のほとんどが左右対称なのは、それがもっとも操縦しやすいからだ。線虫と車がどちらも左右対称のフォルムをしているように、頭を先頭にして左右に動くのが、空間を移動するもっとも効率的な設計なのだ。
だが、むやみやたらに空間を移動していては、エネルギーがすぐに枯渇してしまう。動物が生き残るためには、いつどこに向かって身体を操縦すべきかを決める仕組みがどうしても必要だ。
こうして線虫は、匂いなどの刺激に反応するようになった。その空間移動戦略は、「餌の匂いが強まったら、そのまま進む」「餌の匂いが弱まったら、向きを変える」というシンプルでエレガントなものだ。
空腹な線虫が食べ物の匂いを感知すると、神経伝達物質のドーパミンが放出されて、その匂いが強まる方向に身体を操縦する。温度が上がったり、危険な化学物質を感知すると、アドレナリンとストレスホルモンが放出されてその刺激から遠ざかろうとする。
無事に餌にたどり着いたとしても、食べられる量には限界があるし、いつまでも同じ場所にとどまっているのは危険だ。そこで身体が食べ物を摂り込むと、神経伝達物質のセロトニンが産生されてドーパミンを抑制する。ドーパミンが報酬を追求させるなら、セロトニンは満足感を引き起こすのだ。
このように線虫は、よい気分(ポジティブな情動価)のものに引き寄せられ、嫌な気分(ネガティブな情動価)のものから逃れようとするし、報酬を獲得すると満足して関心を失う。そのように考えれば、これはわたしたちの行動とよく似ている。
これがたんなる擬人化でないのは、線虫が神経系によって身体を操縦する生き物の基本型(プロトタイプ)だからだ。すべての動物は、快を好み不快を嫌うような気分(コア・アフェクト)をもつように設計されている。この快と不快に道徳的なニュアンスを加えると、善と悪になる。
興味深いのは、ここから「嫌な気分はなぜずっと続くのか?」という問いにこたえられることだ。
捕食者の匂いを感知した線虫は、不快になってそこから離れようとする。ところがこの気分をすぐに忘れてしまうと、ちょっと動いただけで逃げるのをやめ、食べられてしまうだろう。それに対して嫌な気分を持続させた線虫は、安全なところまで逃げることができたから、このような神経系が淘汰によって残ったのだ。──いつまでもくよくよと悩んでいるのは、あなたのせいではない。
これはほんのさわりだが、『知性の未来─脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか─』には目から鱗が落ちるような記述が次々と出てきて、エンタテインメントのように楽しめる。わたしたちが好奇心をもつようになったのは脊椎動物の登場からで、シミュレーションするようになったのは哺乳類の登場で説明される。そして霊長類(メンタライジング)、人間(発話)を経て、ついには生成AIのChatGPTに至る。この壮大な歴史を一貫したストーリーで語ることができるのは、知性が突然変異によって生まれたのではなく、一〇億年以上前から、神経系をもつ生き物がブレイクスルーを一つひとつ加え、進化させてきたからだ。
ベネットは「私がこの本を書いたのはこういう本を私が読みたかったから」と述べている。門外漢のこの好奇心が、「わたしたちが読みたい本」を生み出したのだ。
なお、脳科学者の恩蔵絢子氏による訳も正確でわかりやすく、素晴らしい。
(たちばな・あきら 作家)