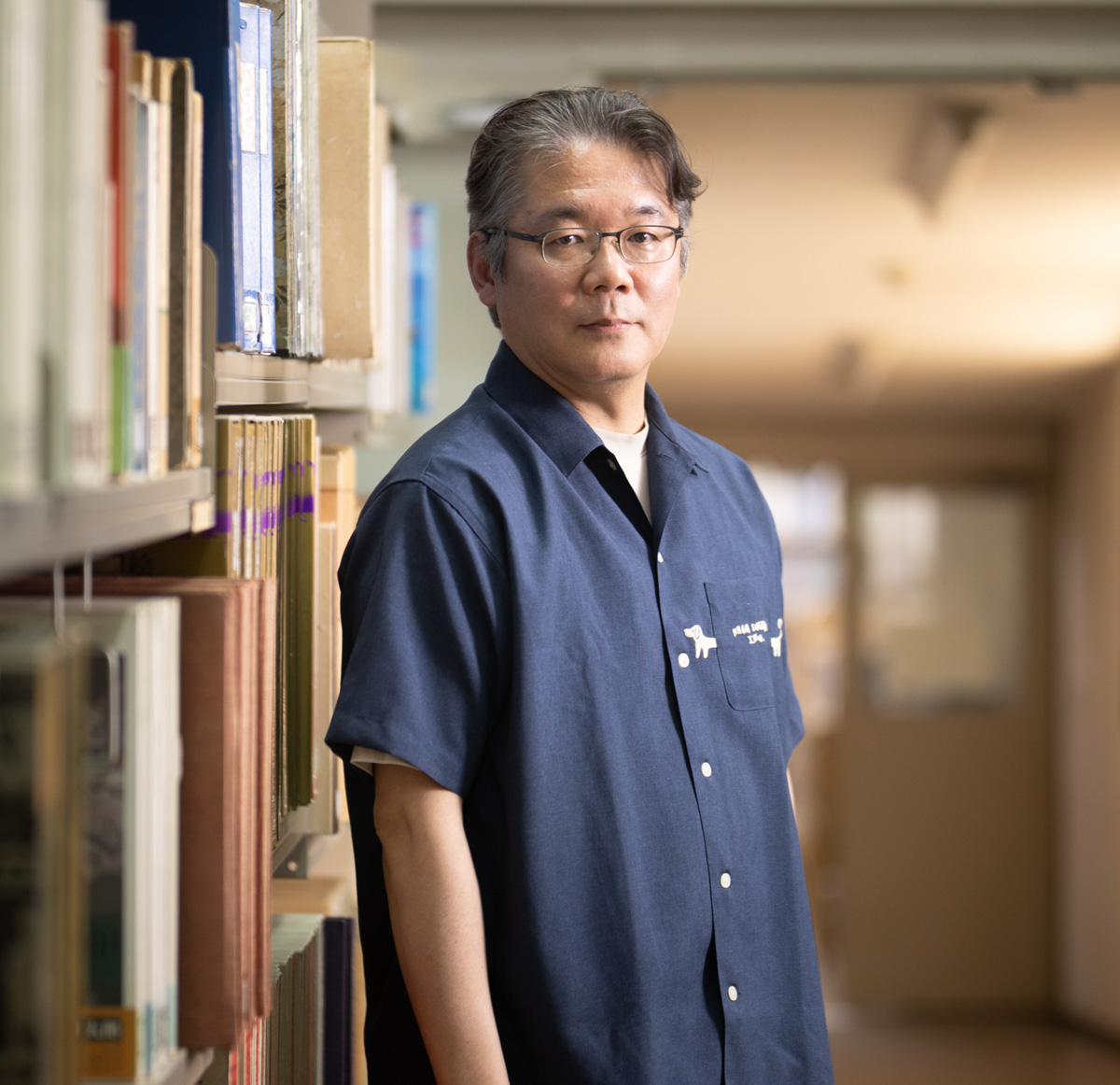インタビュー
2012年6月号掲載
『いつか、この世界で起こっていたこと』刊行記念インタビュー
場所と人との記憶をたどって
聞き手:佐久間文子(文芸ジャーナリスト)
ベラルーシのきのこ狩りは、74000ベクレル/㎡の森で――。世界が変わり、森が変わっても、人びとは生きる。震災後に生きるわたしたちを小さな光でみちびく過去のできごと。深い思索にみちた連作短篇集。
対象書籍名:『いつか、この世界で起こっていたこと』
対象著者:黒川創
対象書籍ISBN:978-4-10-444405-2

――『いつか、この世界で起こっていたこと』では、それぞれ独立した六つの短篇が昨年三月一一日に起きた震災をどこかに響かせながらゆるやかにつながっています。この連作はどんな経緯で生まれたのでしょう。
黒川 もともと、ぼくのなかでゆっくりと用意されていたものがあり、去年の地震や原発事故を通して、そこにかたちが与えられたように思います。自分にとっては、これ全体が、六つの面をもつ、一個の多面体といった作品です。
七〇年代なかば、カウンターカルチャーが下火になっていく京都で、ぼくは一〇代をすごした。中学生のころから、学生街のヒッピー風の喫茶店でアルバイトみたいなことをしてたんです。すると、ちょっと斜めから若者風俗に染まったりもしながら、大人びていくことになりますよね。
「フリーセックス」と言ってる若い男女も、彼らの背景には故郷の田舎町があるわけで、そのギャップは、ぎこちなさを生んでいた。でも、自分が育った土壌を振り返ると、そうした景色は落とせないなと(笑)。あと、原子力への反対意見とか、エコロジーっぽいライフスタイルみたいなものも、そんなところについてまわっていたわけで。そこから現在、そして、さらにもうちょっと未来まで、視野に収めて考えていくには、どうした手だてがあるかなと思っていました。
そうするうちに、大震災がきた。こうなると、それまで考えていた絵巻物みたいな悠長な容れ物では、書こうとする作品の間尺に合わない。あっちでも、こっちでも、物事は起こってきたわけだから。もっと、ぎゅっと、ピカソのキュービズムみたいに、いびつな複数の面によって構成されるオブジェに、おのずと変わったということです。自分の内部では、それは静かな時間でもありましたが。
過去の旅の記憶
――六編にはさまざまな土地が登場します。サハリンなど過去の作品を想起させる場所もありますが、それぞれ実際に行かれたことがあるのですか。
黒川 だいたいはね。ただ、現在の旅より、遠い過去の旅の記憶のほうが、重要でした。
一〇歳、一一歳くらいから、ぼくは、よく一人旅をしたんです。中学生のころは、寝袋を持って、ヒッチハイクや無賃乗車もしながら(笑)。この世界が、どんなところに続いているかに、興味があった。とりあえず、日本国内を行けるところまで行く。たとえば、北海道の積丹半島、泊村。青森県の六ヶ所村も。積丹半島に、まだ一周道路はなかった。ちいさな船でしか行くことができない集落が、北海道の海べりには残っていた。泊村には、よく泊めていただく家があった。それから三、四〇年のあいだに、当時の辺鄙な村、あそこにも、ここにも、原発や核再処理工場ができている。この変化の記憶が、連作全体の下地にあるでしょう。
――過去から現在まで、連作ではさまざまな時間が描かれます。最初に置かれた、七〇年代の京都らしき町が舞台の「うらん亭」が、もともと準備していたという作品ですね。
黒川 イメージの基点といったところかな。ここから始めるんだから、まず、家くらい丁寧に建てておこうと。ボロ家を改修して店を始める話ですけど、まあ、ともかくその建物を描く(笑)。六つほど作品を書き継ごうと思っていたから、どういう順序でそれを書くかが、ぼくには大事でした。
――二つめの「波」では、津波が襲う前後の時間と、メルヴィルの『白鯨』の世界が時空を超えて接続されます。震災報道で紹介されるのは生還した人が過ごした時間ですが、ここにあるのは死者たちの、生を断ち切られる寸前に流れていたはずの時間なんですね。
黒川 そうです。生者として経験することになっていたはずの、死者たちの時間。ぼく自身、そういう時間のなかに立っているのだと、作品を書くことで、気がつきました。
――小説では、津波に巻き込まれた兄と妹が、あさってサーフィンに行く約束をしていたけど、とても無理だろうと互いに考える場面がありますね。
黒川 ええ。彼らは、まだ自分の命が失われたことに、気がついていないんですから。大きな災害に巻き込まれたとき、一人ひとりがとっさに思い浮かべるのは、こうした身近な人たちとの些細なことではないでしょうか。そうやって思う相手がいるというのは、幸福なことだったはずですよね。ただ、もう彼らは、ここにはいない。
核施設のある世界
――次の「泣く男」で、もういちど、「うらん亭」とほぼ同じ時代に戻ります。アメリカの旅の途中に訪ねるハンフォードというのは、巨大な核施設がある場所ですね。
黒川 そう。長崎に落とされた原爆、その原料のプルトニウムを生産した施設です。米国北西部、ワシントン州の内陸の砂漠のなかで、東京都の総面積の四分の三ほどの広さがある。一六歳の夏、ぼくはそこを訪ねた。寝袋を持って(笑)。手引きしてくれたのは、中尾ハジメ(環境社会評論家)とダグラス・ラミス(政治学者)です。
当時のハンフォードのことは、ぜひ書いておきたかった。というのは、いまや、あそこは、おそらく永久に失われた場所だからです。百年かかっても廃炉などの作業を終えられないほど凄まじい放射能汚染を残して、一般人が近づくことさえ許されない場所になっています。
ぼくが行ったときはスリーマイル島の原発事故(一九七九年)より二年前、米国の原子力推進の絶頂期で、自慢の見学施設がありました。日系人の研究者が、稼働中の高速増殖炉の説明を得意満面にしてくれて、帰りには、プルトニウム・ペレットのレプリカをおみやげにもらいましたよ(笑)。
――「チェーホフの学校」には、チェルノブイリ原発事故後のベラルーシで、きのこは子どもが食べるべきものではなくなった話が出てきます。「神風」のサラエヴォ出身の女性歌手は、NATO軍が空爆で使った劣化ウラン弾がもとで妹が亡くなったと語ります。
黒川 はい。ただ、それと同時に、この本では、前半の三作が、わりに少年と男たちの話が中心なのに対し、ここからの後半三作は、どちらかというと女たちが中心の物語になっているでしょう? そういう点でも、これらが書けてよかったなと思ってるんです。
「チェーホフの学校」は、チェーホフの身近な女性たちの話であると同時に、彼の作品を大嫌いだと語る女性詩人アフマートヴァと、その身近にいる女性たちの話。これについては、いろいろおしゃべりを始めると、きりがないから(笑)。
「神風」は、サラエヴォ出身の女性ミュージシャン、ヤドランカとすごした記憶が下地にあります。彼女とは、ぼくが付き人役になって、一緒にドサ回りみたいな旅もした。去年の大震災のあと、彼女は、二〇年以上暮らしてきた日本を離れました。ちょっと寂しくなりもしたけど、しかたがないな。
東京湾の原子力空母
――最後の「橋」の舞台は鎌倉で、黒川さん自身がいま住んでいる土地でもありますね。過去と、現在の作家の視点を行き来しますが、ベストセラー『近代の恋愛観』を書いた英文学者の厨川白村(くりやがわはくそん)が関東大震災でこういうふうに亡くなっていたとは知りませんでした。
黒川 最後は、自分がいる土地を舞台に書きたいな、と。
厨川白村は、左脚が、切断手術を受けて、義足だったんです。鎌倉の海岸近くの別荘で罹災して、義足をつける余裕もないまま、避難しなければならなかった。妻に助けられながら、滑川(なめりがわ)という小さな川にかかる橋を渡って逃げようとしたんだけど、よりにもよって、橋の途中で津波に襲いかかられて、二人とも流されてしまうんです。運が悪かった。その川の上流に、ぼくはいま住んでいる。八キロほど離れた横須賀港には、米国の原子力空母ジョージ・ワシントンが浮いています。いま、日本の原発はすべて止まっているので、国内に存在している本格的な原子炉では、この艦が備える二基だけが稼働中です。これ、東京湾ですよ(笑)。笑っていられませんよね。
――「いつか、この世界で起こっていたこと」というタイトルは、未来と過去、ふたつの時制が混在して不思議な奥行きがあります。
黒川 それで思いだしたけど、ソーントン・ワイルダーの『サン・ルイス・レイ橋』という小説が好きです。むかし、ペルーの町で、侯爵夫人や代書人といった、かかわりのない人たちが五人、たまたま、そこの上を通りあわせるときに橋が落ちる。ただ、それだけの話。それぞれの人生が、消える一瞬に交わっている。作家は、そのことだけを書いています。
(くろかわ・そう 作家)