インタビュー
2014年10月号掲載
〈トマス・ピンチョン全小説〉『重力の虹』刊行記念 インタビュー
永遠の虹――翻訳を終えて
対象書籍名:『重力の虹(上・下)』
対象著者:トマス・ピンチョン著/佐藤良明訳
対象書籍ISBN:978-4-10-537212-5/978-4-10-537213-2
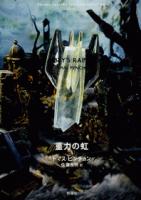
現代世界文学の巨星トマス・ピンチョン。その伝説的な代表作『重力の虹』は全米図書賞を受賞するなど高い評価を受ける一方、「通読不能」「猥褻」とピューリッツァー賞評議会からは授賞を拒否されたいわくつきの超問題作だ。その難物の翻訳に挑んだポップ・カルチャーの研究者でピンチョン研究の第一人者、東京大学名誉教授の佐藤良明氏に話を聞いた。
――翻訳を開始されて七年、ついに刊行ですね。
佐藤 実質は千日、一万時間くらいでしょう。それで足りたかどうか、気にはしています。最初に原書を真っ赤にして読んだのは一九七七年、四十年近く前ですか。まだひと区切り、という感じですかね。終わった気がしなくて、改訂第二版はいつ出すの?と思ってますよ(笑)。
――第二版はともかく(笑)、作品とはどんな出会いだったのでしょうか。
佐藤 僕は大学院生で、現代の最先端にばかり関心が行っていた。その最先端に、バース、バーセルミ、ピンチョンがいた。どれも仕掛けが高級で、日本人の学者の中では、まともな翻訳・紹介はほとんど志村正雄氏の独壇場だったと思います。ピンチョンを読み出したのもその志村さん経由です。
――それらの作家はのちに「ポストモダン文学」というようなくくられ方もしました。
佐藤 ポストモダンって何だ?ってことはありますけどね(笑)。でも、新しい言葉を作り出して対応しなければならないような、革新的な状況はたしかにありました。
――そういう新しい文学のうねり、のようなものが噴出していた中で、佐藤さんがピンチョンに、ことに『重力の虹』にのめり込んだのはなぜだったのでしょう。
佐藤 なぜだったんでしょう。自己破壊的だったせいかもしれない。オレはロックで育った研究者だ、みたいな主張をしたかったのかもしれない。ピンチョンを読むにはいろんなことを知らなくちゃいけないので、視野の狭い専門家にならずにすむかな、という計算もありましたけどね(笑)。
彼は16歳で名門コーネル大学に入ったとき、応用物理工学を専攻しています。だからロケットの軌道制御などについても理解しているし、その数理的な理解から、隠喩を通して、神話文学や、哲学的な意味を膨らませていく知性を持ち合わせている。それだけの資質を持った人がものすごいコストをかけて、何年も何年も、これ一作に集中した。文学作品でこういうことはなかなかないことですから、チャレンジしたくなりますでしょう。
――『重力の虹』を刊行するまでにピンチョンはデビュー作の『V.』でフォークナー賞を受賞し、前作の『49』でも賞をもらっています。すでに評価の高い作家でした。
佐藤 でも、『重力の虹』は特別です。試みのスケールとしても、注入された仕事量からしても、できあがったパラグラフにしても、特別です。震撼します。
第二次世界大戦中に開発されたロケット爆弾、ナチのV2を出発点に、この作品にはそれこそありとあらゆる知識が詰め込まれてます。知識だけじゃない。現代文明に対抗するアナキストの精神が、実にストレートで気持ちいいし。探偵小説からSFからポルノから笑話から、多数のジャンルを貫くところもすごい。その文章がまた、百科事典が語っているようでもあり、濃密な詩のようでもある。
――研究書が多数出る所以ですね。
佐藤 70年代末からアメリカではピンチョン研究を専門とする若い学者がぞろぞろ出てきました。ピンチョンのテクストの背景を調べて解釈を施す、それを始めると、十年、二十年は没頭できる。研究書、専門誌、学会……と盛りあがって、ひとつの「ピンチョン産業」みたいのが出来ちゃった。それだけ人を夢中にさせる要素に満ちた作品ではあるけれど、でも、ここまで言葉にしがみつく人たちの組織って、なにかピンチョンが否定的に扱うテーマの、悪いパロディみたいでしょ。僕らは、みんなその矛盾は引きうけてやってるわけです。
ピンチョンを翻訳するということ
――翻訳は、では難航したでしょうね。
佐藤 一日に何ページ進める、というタイプの仕事の仕方はできませんでしたね。僕は朝の三時には仕事を始めてるんですが、長大なパラグラフと、ああでもない、こうでもないと格闘して、気がつくと午後になっていたりね。会話のところは順調にいくぞ、と思いきや、以前の発言内容が頭にないと、そういうところこそ誤訳してしまう。ものすごく抽象度の高い難解な部分がやっと終わった!と思ってタッタッターと行きたいと思うと、そこに落とし穴があって。
つまり目の前のテクストだけ読んでいても分からないんです。複数の部分が頭に入って、響き合ってきて初めて、オーオーと、どんどん面白くなってくる。熟知によって生じる理解をどう面白く表現するかという意識ができるまでは、だめです。初校、再校となってから「あっ」ということが多かった。だから、まだずいぶん穴があるでしょう、残念ながら。
――原文も、ネイティヴにさえ、かなり難しいですよね。
佐藤 人を選びます。それは事実です。文学の専門家だから読めるということはない。ピンチョンの誘う世界に入っていきたいかどうかが重要で。ウマが合えば、二度目を読むし、二度目はグンと面白くなる。三回読んだらよく分かったという人はけっこういます。そこで、今回の翻訳者としてのひそかな挑戦は、二回読めばわかるものにしようと(笑)。
――と言いますと。
佐藤 まず訳文をまっすぐな日本語にすること。テクストの単語が作っているのは枝葉の部分です。それよりも、その奥にスックリとした幹を立てる。もちろん枝葉は無視できないですよ。言葉でできた表面に、ふつうの小説では要求されない知識が次々に織り込まれているので、これは、註をつけます。二千くらい付けましたか。語釈より突っこんだ解釈も、多くの研究者が共有しているものは、恐れずに盛り込みました。もちろん、どんな読み方をしようと読者の自由ですが。
――それでも二回読まないとわからないですか。
佐藤 そうですね。ただ、何ものにも替えがたい経験になるでしょう。こんな小説、他にないですから。異文化体験と言ったらいいのかな。一週間、二週間滞在して、三週目からジワリジワリ楽しくなってくる異国(笑)。最初はとにかく読みまくって下さい。しばらくして楽しくなってきます。
四冊か五冊分の小説を、強引に関連づけて、一つにまとめたという印象もありますね。緻密なところはものすごく緻密だけれど、相互の連結は強引でね。読者をもパラノイアに誘い込まずにはいない。それを作者は意図的にやっています。そういう風に世界を見てごらん、と。ある意味、破綻しているとも言えます。読者や完成度を置いてきぼりにしてもという狂気がこの作品にはある。以後の『ヴァインランド』や『メイスン&ディクスン』には見られない特徴で、だからこそ中毒的に惹かれる読者を生むのかもしれないですけどね。
――では、翻訳作業は苦痛でしたか。
佐藤 トリップでした。集中できたときには、日常がほどかれていく、失われていく、聖なる中心に入っていく?(笑)……その繰り返し。最高でしたね。なんか叱られそうですけど。これが翻訳かって。厳格な読者は、このフレーズが訳されてない、とか気になるでしょう。
――逐語訳的な翻訳ではないと。
佐藤 最初に「勢い」というか「幹」から日本語にして、その後、枝葉(単語)のレベルでもなるべく裏切らないように調整していきました。でも、単に英語の癖で入ってくるフレーズに義理立てする必要もない。なにしろ魔術的な語りです。一様な方法論では歯が立たない。ピンチョンが掌一杯に携えている意味を、どうやってできるだけこぼさずに他の掌に移し替えるかの勝負だと思って。
――さて、この大作を訳し終えて最初に何をしますか。
佐藤 アメリカ行きます。ピンチョンの影を追います。この本だって訳し終えたとは思っていないし。無責任かな――でも永遠の旅じゃないですか、こういうデカイ文学は(笑)。
(さとう・よしあき アメリカ文化研究)









