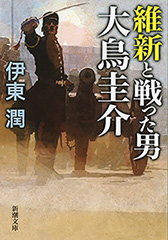書評
2015年3月号掲載
懸命に生きている人たちへのエール
――伊東潤『死んでたまるか』
対象書籍名:『死んでたまるか』
対象著者:伊東潤
対象書籍ISBN:978-4-10-126172-0
戦国ものはもちろん、天狗党を描いた『義烈千秋』、新選組に殺された勤王派の視点で池田屋騒動をとらえた連作集『池田屋乱刃』と、幕末を舞台にした作品でも確かな実力を発揮している伊東潤の新作は、幕府歩兵の伝習隊を率いた大鳥圭介を主人公にしている。
新選組を完璧な組織にした土方歳三に着目した司馬遼太郎『燃えよ剣』が、「将才はない」と断じた影響もあって、大鳥の評価は低く、その実像に迫った歴史小説もほとんど存在していないのが現状である。これに対し著者は、卓越した語学力を使って西欧の医学、工学、兵学を学び、最新兵器を装備した新政府軍を何度も苦しめた有能な指揮官であり、日本で初めて活版印刷で教科書を作った優れた教育者でもあったとして、大鳥を再評価している。
物語は、上方での敗戦が濃厚と知った徳川一五代将軍慶喜が、江戸城へ逃げ帰ったところから始まる。幕府の重鎮は次の策が打ち出せず右往左往していたが、江戸城内で実質的に幕府の海軍を率いている榎本武揚を見た大鳥は、陸軍と海軍が連携すれば、新政府軍と互角に戦えると考えていた。だが、起死回生の戦略を慶喜に拒否された大鳥は、自らが訓練した精鋭歩兵の伝習隊を率いて江戸を脱出し、新政府軍に戦いを挑んでいくのである。
徳川の禄を食んだ旗本が、新政府への恭順を決めた慶喜に従うことを口実に日和見を決め込み、幕府に恩義のある諸藩が、新政府軍が優勢と見るや次々に寝返る現実を目の当たりにした大鳥は、「固定的な身分制度」こそが幕藩体制の生みだした最大の「澱」であり、これが武士の「牙」を抜き、農民以上に「従順な生き物」に代えてしまったと痛感する。
こうした幕末の状況は、裕福な家に生まれたらエリートになる可能性が高い反面、貧しい家に生まれたら十分な教育が受けられず、貧困が子や孫の世代に受け継がれる“階層の固定化”が進み、努力しても門閥には勝てない状況が閉塞感を生んでいる現代と重なる。
それだけに、叩き上げで幕府歩兵のトップになった大鳥が、やはりエリートとはほど遠い「馬丁、陸尺(駕籠かき)、雲助、博徒、火消」を訓練して育てた伝習隊を率い、傍若無人に振る舞う“勝ち組”の新政府軍に一泡吹かせる展開は、痛快に思えるはずだ。
といっても、大鳥の戦いは決して順風満帆ではない。日光へ向かう途上では、巧みな戦術で新政府軍に連戦連勝していたが、練度の高い兵が死んでも補充できず、武器弾薬の補給も十分に受けられない伝習隊は、次第に物量に勝る新政府軍に追い詰められていく。
興味深いのは、新政府軍に負け続けても、大鳥が決して絶望していないことである。
伝習隊は、会津藩国境の母成峠で、新政府軍に惨敗する。当然ながら兵の士気は下がるが、大鳥は、蝦夷地の広大な土地を開拓しつつロシアの南下に備えるという榎本武揚の提案に賛同し、再起をはかろうとする。蝦夷地では軍資金が尽きかけるが、大鳥は殖産興業のプランを示して同志を鼓舞するなど、どれほど窮地に立っても常に前向きなのである。
大鳥は「負けてたまるか」が口癖で、何度挫折しても諦めない執念、というよりも楽天性を持っていた。何度どん底に突き落とされても、我慢すれば再生できる、明るい未来が来ると信じ、どろ水を啜ってでも生き残ろうとした大鳥のしぶとさは、一度転落するとはい上がるのが難しい現代社会を生きる読者にも、勇気と希望を与えてくれるだろう。
同じ幕末を題材にした『義烈千秋』が、志半ばで倒れた者たちへの挽歌だったとするなら、本書は苦しくても懸命に生きている人たちへの、エールになっているのである。
播磨の医師の家に生まれ、努力して武士になった大鳥は、領民を平然と見下す会津藩士や、民が凍死するかもしれないのに町を焼いた松前藩士に怒りを覚える。敵の死にも涙し、領民の幸福を最優先する大鳥の姿は、下々の痛みを知らない世襲議員が、国民への負担を強いている現状への批判のように思えてならない。
(すえくに・よしみ 文芸評論家)