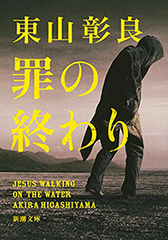インタビュー
2016年6月号掲載
『罪の終わり』刊行記念インタビュー
“相対化”を求めて、ノンフィクション形式(スタイル)を
聞き手・大森望(書評家)
直木賞受賞後初の書き下ろし長編として『罪の終わり』を刊行する東山彰良さん。『ブラックライダー』の前日譚でもある今作は、『流』で初めて東山さんの作品に触れた方にも間違いなく楽しめるエンターテインメント小説です。大森望氏がお話を伺いました。
対象書籍名:『罪の終わり』
対象著者:東山彰良
対象書籍ISBN:978-4-10-120153-5

『流』の台湾版刊行
――『流』の直木賞受賞で生活はずいぶん変わりました?
東山 そうですね。この半年間、地元のテレビやラジオに出させてもらってたので、福岡の街を歩くと、おばちゃんが名前も知らずに声かけてくれたり。「知っとうよ。あんた」みたいな(笑)。それはそれでありがたいんですけど。
『流』は六月一日に台湾版が出ます。もう翻訳は終わってて、原稿を読んだ父と母から、いい訳だとお墨つきをもらいました。複数の翻訳者に第一章を試訳してもらって、うちの親が原稿を読んで、いちばんいい人を選んだ。台湾の編集者も日本語版と細かく突き合わせて、僕が書き間違えてるところも指摘してくれたり。刊行が楽しみです。
ノンフィクション形式の理由
――『罪の終わり』は、二〇一三年に出た大作『ブラックライダー』の前日譚ですね。去年の五月にお話を伺ったとき、初稿はもうできてると聞いて、ずっと楽しみにしていました。
東山 書き上げてからしばらく時間を置いて見直して、じっくり推敲を進めて。ようやく形になりました。
――前作に伝説の黒騎士として名前だけ出てくるナサニエル・ヘイレンが今回の主役ですが、この構想は前から?
東山 いや、『ブラックライダー』を書き終えてから考えました。「ヨハネの黙示録」の四騎士を下敷きにしているので、あの終末世界で、黒騎士(ブラックライダー)以外の三人の騎士の物語も書けないかとずっと考えて、今回は、白騎士(ホワイトライダー)を出しました。
――破滅後の世界で台頭した"白聖書派教会"が差し向ける暗殺者の異名が"白騎士"で。
東山 ナサニエル・ヘイレンが彼らを次々に返り討ちにしていくから、白の反対で黒騎士と呼ばれるようになった、と。あと、赤と青がいるんですけど......どうなるでしょうね。もしかしたらアメリカ大陸以外が舞台になるかも。
――今回は枠物語の構造ですね。語り手として、残された記録や関係者の証言をもとにヘイレンの生涯をたどる本を書いている"わたし"ことネイサン・バラードが登場します。
東山 最初からノンフィクション形式(スタイル)にしようと思っていました。少し前に読んだジョン・クラカワーの『荒野へ』から影響を受けた気もしますね。
――ショーン・ペンが撮った映画『イントゥ・ザ・ワイルド』の原作ですね。アラスカの荒野で死んだ青年の足跡をたどるノンフィクション。
東山 ガルシア=マルケスの『予告された殺人の記録』もやはりジャーナリスティックなスタイルで、そういう書き方をしてみたいと。『罪の終わり』は、妻を失ったネイサンという著者が、自分を救う意味でもこの本の執筆にとりかかり、関係者に話を聞きながら完成させたという体裁です。『ブラックライダー』よりも百年ぐらい前、二二世紀後半が背景ですが、まだ文明が栄えている時点から始まって、小惑星衝突という大災厄が起きて世界が一変し、その数年後ぐらいまでの話ですね。母を殺したひとりの少年が大災害を経て荒野を旅するうち、人々の信仰の対象になっていくまでを書きました。『ブラックライダー』とちょこちょこ関連付けてはいるんですけど、わかる人にわかればいいという程度で。
――むしろ『罪の終わり』から読むほうが入りやすいかもしれませんね。前半は、現代と地続きの二二世紀だからなじみやすいし、少年小説の魅力もある。しかも格段に短い。
東山 前のときと同じで、物語が勝手に終わるまでは書いてやろうと思って。ちょうどいい感じで終わったと思います。
なぜ終末ものなのか
――文明を崩壊させた六・一六の大災厄については、今回はじめてその全貌が明らかになります。小惑星衝突。
東山 想像力があれば、もっとすごい方法を思いついたんでしょうけど。意外とオーソドックスな(笑)。『ブラックライダー』で書きたかったのは世界が滅んだあとだったんで、文明崩壊の具体的な経緯はほとんど触れなかったんですが、今回はそうもいかないからがんばって書きました。読者が「そりゃないだろう」と思わなきゃいいなと。
――可能性としてはじゅうぶんありうることですからね。いまだと、核戦争よりリアルかもしれない。アメリカではこの十数年、ものすごい勢いで終末ものが流行してますが。
東山 何なんでしょうね、この魅力は。僕も無条件でとらわれちゃう。好きなのは、やっぱりコーマック・マッカーシーの『ザ・ロード』。それに『マッドマックス』。『北斗の拳』は僕が中学生ぐらいのときに連載が始まって、ブルース・リー×『マッドマックス』みたいなイメージをみんな持ったと思うんですけど、僕も夢中になって読んだ。
僕の本ではさすがにカーチェイスはさせてませんが、『マッドマックス』のああいう荒野とか、マッカーシーの小説の空気感に惹かれますね。そのせいか、主人公を平面移動させるのが好きなんです。ある問題を解決するにあたって、精神を垂直に掘り下げていく方法もあるでしょうが、僕の場合は、移動の過程でそれを描きたい。
マッカーシーの『すべての美しい馬』も、自動車文化に背を向け、まだ馬にこだわって生きるんだという二人の若者が、リオ・グランデを渡ってメキシコに行く話で。要は、世の中の大きな流れはもう動かせない、自分たちが移動していくしかないという図式が好きなんです。『罪の終わり』も、大きい世界の状況は変えられない。自分自身の罪も変えられないんだけど、移動するつれづれに、彼にどういう変化が起こるか――というお話かもしれません。
小説は、現状をとことん肯定していくものと、現状を否定するものと、二種類に分けられるんじゃないかと。僕の考えだと、太宰の『人間失格』は、自分を肯定していく小説なんですよ。ぶっ壊れても気がふれても肯定する――肯定しないまでも、そこから脱しきれずにいる。主人公は、一応、一歩引いて、自分はこういうふうにして狂った、みたいに見てるんだけど、生まれもった性質や性格から自分を否定したくてもできない人がそういう小説を読むと、癒される気がするんです。自分のかわりに破滅してくれる人を見られるから。
でも、ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』なんかは、自分をとことん否定していく小説だと思います。否定するからこそアメリカ大陸を爆走して、主人公は作家になる。大陸的な小説は、そういうふうに自分の中の嫌いな自分を否定して、旅の経験から新しい自分をつかみとる、空間的にも精神的にも過去の自分を捨ててくるという図式があるんじゃないか。で、僕が好きなのは後者なんです。
『荒野へ』の主人公も、いい大学を出たのに、車を捨て、お金も燃やして、自然の中で生きることを選び、最後はキノコにあたって死ぬんですが、そういう精神の向かい方――そのまま生きていくこともできるのに、それを否定して、新しい冒険に出る、そういう図式が好きなんでしょうね。
越境文学の普遍性
――今の日本の風潮としては、『オン・ザ・ロード』にしろ、『荒野へ』にしろ、むしろ中二病的なイメージで受けとられて、いい加減にしろと言われがちな気がしますが。
東山 そうなんですよ(笑)。その中二病的な発想が大好きなんです。『荒野へ』は、本の中でもいろんな人のインタビューがあって、彼を否定する投書みたいなのも著者はいっぱい受け取るんですが、でもね、いいんですよ。世間の人たちはいろいろ言うんでしょうけど、しょうがない、そういうふうに生まれついたんだから。
やっぱりこういう本は、最後に、物語自体を客観視するというか、相対化する視点があるほうが、僕は好きなんですよ。『罪の終わり』で、インタビュー形式を採用すると、それができると思ったんですよね。主人公にどっぷり感情移入する書き方ではなくて、第三者の目から書いていく。最後に彼は死ぬし、心を通わせる女性とも出会ったんだけれど、でも、それは本当に過去の一瞬のことで、全体としてはこうなんだって総括する視点。自分を相対化し、物語を相対化していく視点がある小説が僕は好きですね。そうじゃないと、もしかしたら本当に中二病的な小説になってしまうんじゃないかとすら思いますね。
僕自身、台湾で生まれて、ほんの短い距離ですが、福岡に移動してきて。それで最近、台湾で生まれて日本で小説を書くとはどういうことなのか、越境文学をどう思うかとよく聞かれるんですけど、いままで考えたことがなかった。ふだんの思考はぜんぶ日本語だし、『流』に関しても、台湾のことをよく知っている日本人が書いた感覚です。越境して書いた感覚はまったくなかった。ただ、少し前に〈すばる〉でリービ英雄さんと対談して、ああ、越境文学ってこういうことなのかと思いました。彼は英語を母国語として日本で暮らしつつ、最新刊の『模範郷』は彼が子ども時代を過ごした台湾のことを書いてるんです。自分が育った、すごく思い入れのある町なんだけど、でも決して受け入れてもらえない。そこに自分の家が確かにあったのに、お父さんもお母さんも西洋人だから、やっぱり自分は台湾人ではない。そういう自分がかつて住んだ家を訪ねていくという。この本にも、最後にやっぱり、それを相対化する視点があるんですよね。
越境文学というか、平面移動をするような小説で、最後にそういう相対化の視点を持ったとき初めて、自分のコンプレックスとか葛藤とか喪失感に、ある程度の普遍性を持たせられるんじゃないか。そうじゃないと、駄々をこねて終わってるような感じがしてしまう。その意味でも『罪の終わり』をこういうノンフィクションの形で書いたのは正しかったんじゃないかなと思ってます。
(ひがしやま・あきら 作家)