インタビュー
2017年5月号掲載
『劇場』刊行記念インタビュー
恋愛がわからないからこそ、書きたかった
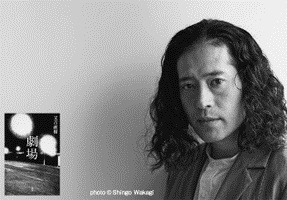
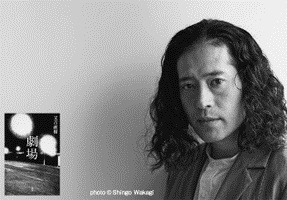
対象書籍名:『劇場』
対象著者:又吉直樹
対象書籍ISBN:978-4-10-100651-2
『劇場』を書き上げて
この小説が自分の中で大きすぎたので、書き上げた今はすごい解放感で、まだ変な感覚なんですけど、やっぱりうれしいですね。解放感がありすぎて、通常の〆切の焦りがなくなって、いま仕事がいろいろ遅れています(笑)。
『劇場』を書き始めたのは、2014年の夏頃でした。冒頭60枚くらいを書いて一旦原稿を置いて、そこから『火花』を書いて、その後またすぐ取り掛かりたかったんですけど、別の仕事もあったりして、それを落ち着かせながら並行して進めて、ようやく出来上がりました。
始めた時点では、まだ小説を書いたことがなかったので、一年の間に『劇場』と『火花』の二作を書けたらいいな、と思っていました。でも、『劇場』の冒頭を書いたところで、これは絶対一年では書き切れないな、と思って。どちらかというと『火花』は衝動的に書いた方がいいように思ったんですけど、こっちはもうすこし時間をかけてやりたかったので、そこで一旦止めたんです。
どうして演劇を書いたのか?
『火花』は漫才師の話なので、自分が知っている世界だったのに対して、『劇場』の演劇の世界は実際に知らないので、劇団関係者の方に話を聞いたり、個人的に取材させてもらったりしながら書いたので、どうしても時間が必要でした。
演劇を書こうと思ったのは、まず演劇そのものが好きだったのがあるんですけど、もうひとつは演劇に向き合っている人に興味があったんですね。お金儲けをしたくて演劇を始める人って、あまりいないじゃないですか。本当に好きじゃないとできない、その純粋さに惹かれました。
僕自身、神保町花月という吉本の劇場で台本を書いていたこともありますし、さらに遡ると6歳の時、父の誕生日に姉ふたりと3人で漫才を作ったことがあって、僕が言ったことを姉が紙に書いて、それを姉たちが父の前で読んだのがデビュー戦でした。「何がオモロイねん」って父には言われましたけど(笑)。
その後、小学校で「赤ずきんちゃん」を関西弁にしてみんなでやったら、父兄にすごいウケたんです。人前で何かをやってみんなが笑うのは気持ちいいんやなって。それは僕にとってすごく大きな体験でした。それで芸人になったんですけど、自分で考えたことをお客さんの前や劇場でやるのは、演劇も近いですよね。
演劇で食べていくのは実際かなり難しいし、医療関係の仕事でもないから、直接誰かの命に関わるわけでもないし、「なんでそんな大変なこと、苦しみながらやっているの?」「やめたらええやん」と思う人が多いかもしれないけど、僕は全然そう思っていなくて、ムチャクチャ意味があると思うんです。
同時に、周囲に理解されない状況で自分の好きなことに取り組むのは、ある意味すごく身勝手なことだったりもして、実際それに振り回される周りの人もいるんでね。僕が昔から好きなテーマのひとつに「誰も悪くないねんけど、なんとなくみんな苦しんでる」というのがあって(笑)。そういう人を見るとほっておけないし、たぶん自分がそういうタイプの人間なので、どうしたらええんやろな、という悩みどころでもあって、僕にとって書かずにはいられない重要な主題でした。
恋愛がわからないからこそ、書きたかった
スポーツ番組でご一緒している中畑清さんが「今度書いたの、恋愛小説なんだろ?」「おまえ、結婚もしてないくせに」とおっしゃっていて、「ほんまにそうやな」って(笑)。でも、恋愛小説は、恋愛がうまい人だけが書くものでもなくて、わからんから書く部分もあると思うんです。
恋愛って何なのか、いまだに僕はよくわかっていないんですよね。一見シンプルなようで複雑な構造で。実際うまくいってないから結婚してないわけで、だからと言って、ほっとかれへんというか、どうでもいいわ、とも思えないんでね。
自分が生まれ育ってきたことを振り返ると、両親がいるわけじゃないですか。両親が恋愛したかどうかはわからないですけど結婚して、そういう男女の関係性の上で僕が存在しているんで。やっぱり重要な永遠のテーマで、子供の頃から常に関心がある三つのことのうちのひとつに入っているのかなと思います。
主人公の永田は沙希と出会って、彼女の存在に救われるんですけど、彼が演劇にのめりこんでいくにつれて、沙希との関係がどんどん変化していきます。「人間が変化する」というのも、僕がずっと気になっていることのひとつです。よくいつまでも変わらないと言われる人がいますけど、そこには覚悟や大きな意志が働いていると思うんです。人間って、普通は絶対変わるんで。いろんな影響を受けたり歳をとったり、そもそも世界自体が変わっていくから、自然にしていたら、そこに混ざる自分の色も一緒に変わっていくんです。
恋愛の場合、自分が変わるだけじゃなくて相手も同じように変わっていくので、戻したくても、もう戻られへんことがあって、最初はふたりとも黄色だったのに、どんどんいろんな色が混ざってきて、わけわからん状態になることって、けっこうあるじゃないですか。それが書けたのは、やっぱり小説というあれだけ長い文章だからこそだと思います。
10代のとき書いた、幻の小説
時間の流れや感じ方も、人によって全然違いますよね。みんな、これから先どうなるかは気にするけれど、すでに起こったことは、もう過去のことやからって、わりと割り切れるじゃないですか。僕は過去だからといって、なんかほっとかれへんというか。
物事を判断する時も、今こうして36歳の僕がバトンを渡されているので、この僕に決定権があるんだけど、20代の頃だったら、全然違うジャッジをくだすかもしれなくて、この今の僕の一存で決めていいのかという迷いもあるんです。もしかしたら、20代の僕のほうが判断力が上だった可能性もあるじゃないですか。時間の経過と成長が一緒にあるというのを、いまいち信用できないところがあって。若い頃かっこよかったのに、おっさんになってダサいな、と思う人がいるように、自分がそうじゃないとは言いきれへんから。だから昔の自分が決めたことを、今の僕が簡単にやめてしまうのはどうなのかな、と思ったりもします。
20代の下積み時代はとにかく時間があって、ひとつのことをずっと考えていられたから、僕にとっては必要な時間でしたね。当時は遊ぶ相手もいなくて、ひとりでずっと歩いているみたいな日常で、それがよかったんかなって。
僕、ずっと小説は書けません、と言い続けてきたんですけど、なぜかというと、18、19の時に、百冊くらい本を読んできたし、小説一本くらい書けるかなと思って、原稿用紙になんとなく頭に浮かんだ物語を書き始めたら、全然書けなかったんです。それで「小説って難しいんやな」と思って、また本に戻ると、「書き出しってこんなに美しいんや」「会話のあとはこうやって地の文に戻るんや」って発見があって、読書がさらに面白くなって、これはもうとんでもない人たちの世界だから、自分は読む側に回ろうと決めた、という。
その書きかけの原稿がこの間、引っ越しをした時に出てきて読み返してみたら、まったく覚えてなかったんですけど、今回の『劇場』と『火花』を足したみたいな設定だったんです。それでちょっと笑ってしまって。その頃の僕は、まだ上京したてで何も経験していなくて、想像で書いている部分が大きいはずなのに、不思議やなあって。
「書きたいこと」と「わかりやすさ」
小説を書くのが難しいことは、理解していたほうだと思うんですけど、やっぱり小説って難しいですね。『火花』を書いて、「あ、こうやって小説って書くんや」という感触は確かにあったのに、今回『劇場』に向き合うなかで「あれ、どうやって書くんやったかな」と思うことは何回もありました。
「書きたいこと」と「わかりやすさ」のあいだで、どうやって書くか、ずっと考え続けていたような気がします。「新潮」みたいな文芸誌に載せていただく小説は、読者を意識しすぎるとよくないことは客観的にはわかるんです。僕も好きな作家さんには、読者を意識せず自分の書きたいことを全力で書いてもらいたいし、それを自分なりに楽しみたいので。
ただ、自分が書き手にまわった時には、ムチャクチャ読者を意識したいんです。それはびびっているのとは真逆で、意識するほうが難しくなるから。自分の書きたいものを書いたうえで、なおかつ人に伝わるようにすることは、今回かなり意識して書いたつもりです。
僕の情熱を伝えるだけなら、絵の具に手をつっこんで紙にバチンとぶつけて、「ここから僕の心を読みとってください」というのでもいいと思うんですけど、小説だから、文字と日本語を使っている以上、最大限伝えることから目をそらしたくないなって。そのへんを考え出すと、さらに大変になったというのはあるかもしれません。
『火花』が難しかったと言われて
僕が読んできた本は、文体が工夫されているものが多かったので、『火花』のときも悩んだんですけど、編集者さんと話して、普通に書いて映像が浮かぶ文章も珍しいから、そのままでいいんじゃないかと言ってもらって、じゃあそのまま書こうと思ったんです。だから、『火花』では自分の思いをまっすぐ言葉にしたつもりだったのが、普段劇場に来てくれる方やテレビで応援してくださる方が読んで、ちょっと難しかったという反応を聞いて、少なからず僕は驚いたんです。自分では難しいと思って書いていなかったから。
一方で、僕の好きな作家さんたちに「そういう声があって、気になっているんです」「せっかくお金出して買ってくれたのに、難しくてあまりわからなかったら、かわいそうやなと思っちゃうんです」と話したら、「『火花』はそんな簡単な話ではないかもしれないけど、言葉が複雑だったり難しいとは思わないし、そこまで合わせに行くとバランスを崩すから、気にしない方がいいよ」っていう声がほとんどで。
その両者の意見を聞いて、「どうしたらいいんだろう」という思いはありましたね。そこには、僕が舞台に立ち続けてきたことも影響していると思うんです。たとえば、僕らのことをよく知っている100人くらいの人の前でやる場合は、自分の好きなひとりよがりなネタでも許されるんですけど、それが500人に広がっただけで、まったくウケなくなるんです。で、ウケないというのは傷つくんです。
そこで、どうやったら楽しんでもらえるか、ずっと考えてきたので、だいぶ広い劇場に自分の小説を「今回これです」って持っていくときに、どうしようかなという思いは、正直ありました。
表現の場を求めてあがく主人公を書くことで
『劇場』の主人公はずっと表現の場を求めていて、自分の表現を突き詰めたいという欲求と、もっとお客さんを呼びたい、注目を浴びる大きな舞台でやりたい、という両方の意識が強いんです。でも、その場が与えられなくて、そのためにはもっと考えたり、作品の強度を上げたりしないといけないから、本人の責任も僕はあると思うんですけど、そうやってあがいている主人公を自分が書いていくわけです。
そういう主人公の状況に対して、僕自身はムチャクチャいい劇場を用意されていて、みんなが「二作目書けるのか」と気にしてくれている状況で、何をびびってんねんって(笑)。そもそも芸人になるのを決めたのも、小説書くって決めたのも自分で、表現の場を求めていたはずの人間が、おびえている場合じゃないな、と。だから書き進めていく途中で、小説自体が僕を鼓舞してくれた瞬間が何度もありました。
自信をもって仕上げたものを人前で発表できるのは、そもそも喜びで、もちろん恐怖も伴うから初舞台はすごい怖かったし、そういうものなんですけど、発表の場が与えられて、打席に立てることがどれだけ恵まれているのか僕自身よくわかっているんで。それこそ、10代や20代の頃の自分が厳しい状況に抗って、やめなかったおかげで今、僕の番が来ているから、それをちゃんと背負ったうえで作品にしないといけないな、という思いはすごいありましたね。
何度も書き直すなか、最後に生まれた場面
一旦書き上げた後、時間をかけて推敲をして仕上げていきたい、というのは最初からお伝えしていました。そのほうが間違いなくよくなるだろうと思ったのと、お笑いでネタをつくるときも、何回も直すなかで新しい発見があって、そこから広がっていくことがあるのを経験していたので、小説でもやってみたいなと思ったんです。実際に直していくなかで大きく発展して膨らんでいったところもあったし、逆に削ったところもありましたが、それはもう絶対やってよかったなと思います。
この場面はもっと詳しく書き込もうという直しの段階で、考え込むことはあまりなかったかもしれません。その時点で小説のなかで書いていることと同じくらい、書いていないことも、もうすでに作品の世界のなかにはあったので、どこを出してどこを引っ込めるかを考えればよかったんだな、というのは今回、推敲を重ねるうちにわかったことでした。
印象深い場面はどこか、と聞かれると、思い入れがあるところはいっぱいあるんで、どこかな。「あそこがよかった」と言ってもらう場面が人によって違ったりして、全部うれしいんですけど(笑)。最後の最後に書き足した、永田が演劇をやっていくうえで、自分は「こんな瞬間に立ち会うために生きているのかもしれない」と感じる高円寺の駅前の場面があって、そことかは好きですね。
あそこがあることで、永田のことをすこしだけ好きになれるというか。終始、おまえ何してんねん、と言いたくなるような男なんですけど、ああ、こういう一面があるんやったら、わからんでもないなって。小説の精度や強度として、どのくらい読者に伝わっているのかはわからないですけど、自分としては好きですね。
(またよし・なおき 芸人・作家)










