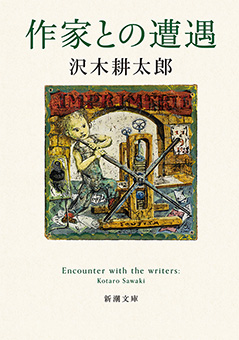書評
2018年12月号掲載
「読むこと」のレッスン
――沢木耕太郎『作家との遭遇 全作家論』
対象書籍名:『作家との遭遇 全作家論』(新潮文庫版『作家との遭遇』)
対象著者:沢木耕太郎
対象書籍ISBN:978-4-10-123534-9
かつて沢木耕太郎は、ノンフィクション・ライターという仕事を何よりも「視る人間」であると規定した。ペンを握る前に、意識的に視ることが重要である、と。
書き手としての沢木を特徴付けるのは、その専門性の無さにある。彼はある分野のインナーサークルに入ることを頑なに拒絶し、アマチュアであり続けることに美学を見出している。取材テーマも自身の関心と興味が〈ひっかかる〉ものを求めることで自然に決まっていくという。
彼はある時は相場師を描き、ある時は日本ダービーに出走する馬の世話をし、ある時はボクサーと寝食を共にした。一見するとなんの共通点もない題材であっても、すべてにおいて沢木が誠実に取材対象を見続けるという一点は共通している。その上で、いかにして書くのかを自らに問い、方法にこだわり、徹底的に細部を描くことを通じて、ひとつの作品世界が提示される。
この作家論集もそれらの特徴とプロの「文芸批評家」にはないアマチュアの美学が貫かれていると言えるだろう。本書の中で、沢木は第一義的に「読む人間」として存在している。
大学の卒業論文として仕上げたアルベール・カミュ論然り、向田邦子、山口瞳、色川武大、吉行淳之介といった接点があった作家然り、彼のノンフィクション同様、一見すると雑多だが、彼がどこかで〈ひっかかり〉を覚えた作家に関心は向かう。
「読むこと」は時に、取材してすなわち、視ることを通じて書くことと同様、容易なものとして扱われる。およそテキストを読むことと無縁のまま人生を終える人はいないし、本を大量に読むだけなら沢木以上に読んできた人間などざらにいるのだから。では、「読む」ということは誰にでもできる簡単なものなのだろうか。
「読むこと」を考えるにあたり、補助線を引いてみよう。優れたノンフィクションとは何か。私はその条件の一つに「取材を受けた当人ですら知らなかった当人の姿を描きだし、一つの世界観を提示すること」があると考えている。人は思いの外、自分のことを知らない。だからこそノンフィクションの書き手は視ること、インタビューで話を聴くこと、そして書くという行為を通じて、彼ら自身も知らなかった彼らに接近する。取材を受けた当人から「そんなことは知っている」あるいは「自分の思い通りに書いてくれた」と思われた時点で、作品としては失敗なのだ。
「読むこと」も同じである。「読む人間」としての沢木が試みているのは、彼がそれまでの作品で積み上げてきた世界と変わらない。〈ひっかかり〉にこだわり、作家自身も知らないであろう作家の姿を浮かび上がらせることに執着する。
例えば向田邦子だ。一九八一年に書かれた向田論で沢木は、彼女の鮮やかな文章がもつ特徴を、語りたいことをシーンで描き出す巧みさにあると指摘した。
〈向田邦子が描く対象は、表情、色つや、匂い、などといった細部の急所が的確に押えられ、その結果、読み手は話の流れに沿って、登場してくる人や物や風景を、いとも簡単に映像化することができる〉
時代を代表する脚本家であり、直木賞作家でもあった彼女の文章の上手さは一読すれば誰もがわかることだ。重要なことは、沢木の読解をもって新しい視座が与えられることにある。この章を読むと、向田邦子のエッセイは単なる身辺雑記ではなく、細部を積み上げることによってシーンを描き、シーンの連続によって言いたいことを表現するという「ノンフィクションの教科書」になる。
思うに彼にとって「読む」とは、彼自身が書いていく上で、言い換えれば生きていく上で切実な問いについて、作家との対話を試みる時間である。挿話のつなぎ合わせではなく、シーンの連続によって対象をいかにして描くのか。新しい方法の冒険をしていた当時の沢木にとって、向田作品は格好の「教科書」だったのだろう。
本書を読み終えて嘆息するのは、沢木の文章が持つ強度だ。真摯さに貫かれた読解は、個々の作家「論」をはるかに超えて、作家その「人」の本質を描き出す。それゆえに初出から何年経っても古びることはない。彼が切り開いた道を読み手としても書き手としても知っている私にとって、この論集はどの作家を読むべきか以上に、いかにして「読む」べきかを指し示す道標として存在し続けるだろう。
(いしど・さとる 記者/ノンフィクションライター)