インタビュー
2019年1月号掲載
『国家と教養』刊行記念特集 インタビュー
本当の教養人だったら、こんな本は書かなかった
270万部超を売り上げた大ベストセラー『国家の品格』出版から13年。
今度は「教養」というテーマに挑んだ藤原氏が、ユーモアたっぷりに明かす執筆の舞台裏。
対象書籍名:『国家と教養』(新潮新書)
対象著者:藤原正彦
対象書籍ISBN:978-4-10-610793-1
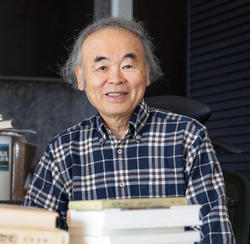

――270万部以上を売り上げた『国家の品格』の出版から13年。ようやく「第二弾」が実現しました。
藤原 品格の次は教養かな、とは思っていましたが、なかなか書けず、女房には「いつまで学者やってるの! お父さんみたいに適当に見切りをつけて書き始めないと」などと言われていました(笑)。確かに父(新田次郎)のように小説家なら、資料になる本をいくつか読んで想像力で膨らませて書く、ということができます。しかし、私は関連するテーマの本を読み尽くし、調べ尽くしてからじゃないと書き始められないんです。
――それで時間がかかってしまった、と。
藤原 ええ。教養をテーマにした本はずいぶん読みましたが、だいたいは文学畑哲学畑の、すでに教養を十分に身につけた人が教養の衰退を嘆く体のもの、あるいは教養のハウトゥーもので、本質に迫っていると思える本はなかった。
教養を巡る問題の本質は何か。それは、なぜかつては重要と考えられた教養が衰退してしまったのか、どうすれば再生させられるのか、そもそも現代に相応しい教養のあり方とはどういうものか、を考えることです。「教養」本はみんな「教養とはなんぞや」という定義論から入りがちですが、それがそもそもの間違いの元なんです。言葉による定義論をやる限り、「その定義づけを行っている言葉の定義はなにか」という無限ループに入りこむことになって、際限がなくなってしまう。そこに拘泥せず、「教養」の効能、限界、再生の可能性を解き明かすという本質に集中しました。
――本書の第二章から第五章は、「教養の世界史」とも言うべき内容ですね。
藤原 まず歴史的に「教養」がどのように扱われ、保持され、どのように機能し、どこに限界があったのかを探るべきだ、と考えました。それがないと、この本自体が根無し草みたいな論考になってしまいますから。
大衆文化こそ大事な教養である
――本書の中で藤原さんは「教養の四本柱」を挙げています。独特なのは、「人文的教養」「社会教養」「科学教養」につづいて、「大衆文化教養」を挙げている点です。
藤原 最初の三つは、いわば現代社会を生きるために必要な知識の話。でも、本当に大事なのは、この「大衆文化教養」という最後の部分なのです。
どうして日本の教養層はひ弱だったのか。戦中にはあっさりと軍部にだまされ、戦後はGHQに洗脳され、現在は新自由主義イデオロギーの虜になってしまうのか。それは、西欧崇拝に基づいた「教養」が上滑りのもので、本当に身についていないからです。日本人にとっては、日本人の情緒や形と一緒になった知識でないと、本当には身体にしみこまない。つまり、ホンモノの教養とは言えないのです。
『国家と教養』の中でも書きましたが、戦中は体制支持派だったのに戦後はあっさりと戦前戦中批判に転じ、戦争協力者を糾弾して地位を得ようとした知識人には事欠きません。「私はだまされていた」と語った武者小路実篤だけでなく、教養主義のチャンピオンとも言うべきドイツ文学者の中にも、リルケやヘルマン・ヘッセの翻訳者でありながら戦時中はナチス支持で戦後はどこ吹く風、などというケースがたくさんあります。
――藤原さんには「教養」を尊重しつつも懐疑的な、アンビバレントな感情があるようですね。
藤原 実は、私は「自分の好きな本を気ままに読み、それが教養として積み上がる」というような読書の仕方を大学を出てからしたことがないんです。数学の研究と並行して文学的な仕事を40年も続けてきましたが、読書はいつも「何かを書くための調べ物」でした。だから、教養人とはまったく言えません。
本当を言えば、そんなに読書家とも言えないのですよ。小学生の時に少年少女世界文学全集を読破したこと、中学時代に日本文学の文庫本や講談本を乱読したこと、高校時代に父のところに送られてきていた「新潮」「群像」などを時折読んだりしたことくらい。高校時代はサッカーの部活動と受験勉強で忙しかった。大学に入って、全く読んでいなかった西欧の小説を次々に読みましたが、2年生の秋からは数学漬けの生活になり、それが大学院を修了して都立大の助手になるくらいまで続いた。その間は阿修羅のごとく数学に打ち込んでいましたから、楽しみのための本なんてほとんど一冊も読んでいなかったんです。
――高校時代は自分が西洋の小説や哲学を読んでいないことにコンプレックスを感じていたそうですね。
藤原 後に東大の哲学科に入った同級生が、ものすごく西洋の小説を読んでいました。彼が『チボー家の人々』を読んでいて、「主人公のジャックが......」なんて語っているのを、私はさもすでに読んでいるようなふりをして頷いて聞いていたことがあります(笑)。恥ずかしくなってそのまま吉祥寺の本屋に走り、白水社版の『チボー家の人々』全五冊を買いました。以来60年、その本は開かれることのないまま、私の本棚に差さったままです。トルストイの『戦争と平和』も同じ運命を辿りました。
また、大学1年の時に中学の同級生の友人が、「(旧制高校の三大教養書である)阿部次郎の『三太郎の日記』、西田幾多郎の『善の研究』、倉田百三の『愛と認識との出発』を読まないと大人になれない」というのを聞いて手に取ってみたら、あまりにもつまらなくてどれも20頁くらいで投げ出してしまった。
私にとって数学は難しくても面白いものでした。読めば読むほど視界が広がっていくのが分かる。しかし、これら「旧制高校の教養書」は面白くもなかったし、視界が広がる感じもしなかった。
――でも、この友人には恩義があるそうで......。
藤原 ええ。彼は私を哲学に目覚めさせることには失敗しましたが、初めてストリップ小屋に連れて行ってくれ、見事に性に目覚めさせてくれました(笑)。看板に「関西風特出し」とか書いてありましたね(笑)。
アニメと歌謡曲も
――伺っていると藤原さんは、日本の知識人に多い「西洋文学を読み込んで人格を陶冶する」というタイプとは、まったく違った知的来歴をお持ちのようですね。
藤原 私にはどうも、西洋的教養の小説や哲学がしっくりこなかったんですね。講談本の方がずっとしっくり来た。でも、近代の歴史を見ると、西洋由来の教養を積んでいた知識人たちがあっさりとだまされたり転向したりしている一方、そんな教養とは無縁の庶民たちは現実的でたくましく、かつ情緒や日本人としての形を保った生活をしていた。講談本や大衆文学、そして伝統の芸能や芸道には、日本人の基本的な価値観がたっぷりと表現されています。こうした大衆文化が、日本の庶民の際立って高い道徳や情緒を支えてきたのです。
西洋由来の教養を積み重ねることより、日本の大衆文化にふれて日本人としての情緒や形を刷り込むことの方が現代においてもずっと大事だということを確信しました。『国家の品格』で論理より情緒と唱えましたが、教養に関しては第一、第二、第三の柱が論理で、第四の柱が情緒です。すなわち『国家と教養』は『国家の品格』を補完するものとも言えます。
――『国家と教養』の中では、「君の名は。」のようなアニメや、歌謡曲も称賛されていますね。
藤原 私はもともとアニメを見るような人間じゃなかったんですね。子育て中に子供と一緒に「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」を見ていたくらいで。だから、薦められて「君の名は。」を見たら、とても感動しました。と同時に、アニメでもここまでの情緒と美を盛り込むことが出来るということに驚いたのです。
日本人は本当に特殊で、こうした大衆の娯楽においても情緒と美を自然に盛り込んでしまう。昭和期の歌謡曲などにも情緒に溢れた良い曲がたくさんある。私はいつも昭和の歌謡曲を自宅で歌っています。女房が嫌がるので、お風呂の中でですが(笑)。西洋音楽で育ち、世界中の文化を見聞してきた文化人類学者のレヴィ=ストロースも、日本の歌だけには「もののあわれ」があり、感動したと言っています。
――バランス感覚とユーモアの大切さも力説されていますね。
藤原 これは80年代にケンブリッジ大学で教えていた時のエピソードなんですが、知り合いの天才数学者に「ジェントルマンにとっていちばん大切なものは何か」と聞いたら、彼は間髪入れずに「ユーモア」と答えた。天才の言うことは怪しいので(笑)、英国人に会うたびに聞いて確認してみました。そうしたら例外なく、ユーモアがいちばん大事という意見に「同意する(I agree)」と答えたんです。
ユーモアが成り立つためには、自分をいったん状況の外に置き客観視してみる、という作業が必要になります。それは自分中心主義では成り立たない。必然的に、バランスの取れたものの見方をするようになるわけです。教養によって大局観を磨き、大衆文化に親しんで俗世間の実相を知れば、自然にユーモアとバランス感覚も身につくはずです。
『国家の品格』は品格なき著者による品格論でしたが(笑)、『国家と教養』は教養なき著者による教養論です。私が本当の教養人なら、こんな本は書いていません。教養のある側、ない側両方のことが分かるから、その間をつなごうと思った。国民が教養層と非教養層に二分されたことは、第一次、第二次大戦の一因でしたし、そもそも国民一人ひとりが教養に基づく大局観を持っていないと、民主主義はポピュリズムに成り果てます。この本によって「教養」にあらたな息吹が吹き込まれる事を願っています。
(ふじわら・まさひこ 数学者)










