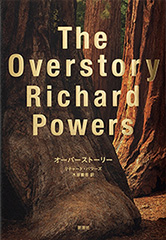書評
2019年11月号掲載
読めば、以前には戻れない
リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』
対象書籍名:『オーバーストーリー』
対象著者:リチャード・パワーズ著/木原善彦訳
対象書籍ISBN:978-4-10-505876-0
〈いい物語は人を少し殺す。人を前とは違ったものに変える〉
一九世紀半ばにアイオワ州に入植した祖先が植え、以来、父の代までその変化を定点観測的に撮り続けた栗の木の写真。千枚もの写真をパラパラとめくって眺めるのが好きだった少年ニコラスは、長じて〈変わったものを作って一生を送りたい〉と思うようになる。
1948年、中国の家族のもとを離れ、渡米。携帯電話の開発に成功するも自死を選ぶことになる父親から、過去・現在・未来を象徴するロートス・松・扶桑の彫刻が施された三つの翡翠の指輪と、阿羅漢を描いた書画の巻物を見せられた九歳のミミは、〈時間は、目の前で先へ先へと伸びていく直線ではなく〉、あたかも年輪のごとく、自分を〈核とした同心円状の柱で、現在は最も外側の環に沿って外へ外へと漂い出て行く〉という知見を得る。
父親からカエデの木を〈同胞(シブリング)〉として与えられた1963年生まれのアダムは、高校三年の時に一冊の本と出合い、その著者である学者のもとで心理学を学ぶ道に進む。
弁護士のレイと速記者のドロシー。幾たびもの別れと復縁を繰り返し、やっと結婚できた愛するドロシーに、レイは結婚記念日のたびに何か庭に苗を植えることを誓う。
ベトナム戦争に従軍し、爆発する飛行機からパラシュート降下を試みて失敗するも、一本のベンガルボダイジュによって命を救われたダグラスは、皆伐地にダグラスモミの苗木を植える仕事に就く。
固体物理学の学位をたずさえてインドから渡米した父親と一緒に、七歳にしてコンピュータのキットを組み立て、プログラミングを始めたニーレイは、十一歳の時にオークの木から落ちて半身不随に。二年の飛び級で入った大学在学中にフリーウェアのゲームを作り、コンピュータ・ゲームの〈開拓者(パイオニア)たちの間でちょっとした伝説と化す〉。
生まれつき内耳に奇形があり、発語にも苦労するパトリシアは、父親から植物愛を受け継ぎ、長じて博士号を取得するのだが、木々がコミュニティを形成し、助け合っているという内容の論文が酷い批判を受け、大学での職を失う。自殺まで考えるのだが、その後、森林レンジャーの仕事を得て、森の中での科学者との出会いにより、再び研究者の道に戻る。
早い結婚と離婚、おまけに薬物依存症。大学の最終学年に至るまで自堕落な生活を送っていたオリヴィアは、1989年12月12日、不用意な感電により七十秒間死ぬ。蘇った彼女には精霊の声が聞こえるようになり、その声にいざなわれるように、古木を守るため人々が座り込みを続けているカリフォルニア州ソラスという小さな町を目指すことになる。
リチャード・パワーズの『オーバーストーリー』は、こうした何らかの形で樹木と関わりを持つ人々の来し方を描く「根」の章を経て、彼らの運命が交わる「幹」へとつながっていく。主要登場人物らの生が、木々の根のように、互いが互いを知るずっと前からつながっていることを、この小説はじょじょに明らかにしていくのである。
若くして生家で自分の作品と隠遁しているかのような暮らしを送っているニコラスと、ソラスを目指す途中で出会い、行動を共にしていくオリヴィア。公園にある松の大木が、当局によって強引に伐採された出来事がつなげるミミとダグラスの縁。「ミマス」と呼ばれる巨木を伐採から守るため、一年近くも地上六十メートルの樹冠で生活するオリヴィアとニコラスのもとに、樹木保護家の"狂信"についての聞き取り調査のため訪れるアダム。この五人によってなされる"正義"と、それが引き起こす悲劇。活動家としては合流しないレイ&ドロシー夫妻やニーレイも、いずれ自分と樹木とのつながりを自覚することになり、そうした彼らの中心にあるのが、パトリシアの著書『森の秘密』なのだ。
冒頭の引用文どおり、この長い物語を読み終えた時、植物の命に無関心だった自分は少し死に、樹木や森を見る目や思いが変わる。以前の自分には戻れない。そして、地球環境の現状に絶望する。もう、手遅れなのではないか。しかし、ラスト近くで、〈生命は未来へ話し掛ける方法を持っている。それは記憶と呼ばれる〉とあるとおり、『オーバーストーリー』を読んだわたしたちが〈記憶〉という根で深くつながっていき、この作品を次代に伝えていく役目を担えたら、もしかすると......。これは人類のための小説ではない。地球上に在る、ありとあらゆる生を守るための小説なのだ。だから、大事な小説なのだ。