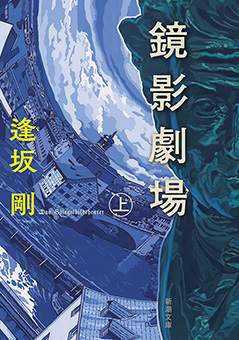対談・鼎談
2020年10月号掲載
逢坂剛『鏡影劇場』刊行記念対談
ホフマンは二度おいしい
逢坂剛 松永美穂
(作家) (早稲田大学教授・ドイツ文学翻訳家)
十九世紀ドイツの文豪E.T.A.ホフマンの生涯を、現代日本を舞台にビブリオ・ミステリーとして蘇らせた『鏡影劇場』。
この巨編を上梓した逢坂氏と、ドイツ文学者の松永氏が、時代を超えたホフマンの魅力とミステリーとしての醍醐味を語り合う。
対象書籍名:『鏡影劇場』
対象著者:逢坂剛
対象書籍ISBN:978-4-10-119520-9/978-4-10-119521-6


逢坂 小説でE・T・A・ホフマンを書きたいという気持ちは、若い頃からずっとあったんです。ところが、なかなか調べものが進まなくて、その間に資料ばかり集まってしまいましてね。
松永 私はホフマンに全然詳しくなくて、逢坂さんに、こういう本を知ってますかとか聞かれても、知らないことだらけで。逢坂さんはどうしてこんなにご存じなんだろうと思っていました。
逢坂 松永さんは、ドイツ文学でもホフマンはご専門ではないんですね。
松永 専門はドイツの戦後文学なんです。大学院生の時に、当時まだドイツが東西に分かれていましたから、東独の反体制作家に興味を持ちまして。
逢坂 わたしは、ドイツ文学者じゃないし、ホフマン一本でしたけれども、それなりに大変でした。たとえば、これはホフマンの書簡集第一巻ですが、取り寄せてみたらフラクトゥール(亀甲(かめのこ)文字)なんです。普通のドイツ語だってすらすら読めるわけじゃないのに、本当に古文書を解読するようなものでした。
松永 邦訳は出ていないんですね。
逢坂 全く出てないんですよ。幸いにも、部分的に英訳が出ていたので、それはずいぶん助かりました。何度、松永さんに電話して、ドイツ語を教えてもらおうと思ったことか。
松永 電話してくださればよかったのに(笑)。未邦訳の資料に当たられているというのは、本当に素晴らしいことです。ホフマンについての新しい情報が、びっしり詰まっているんですね。
逢坂 ホフマンを巡る報告書の部分は、ほぼ事実に即しています。ホフマンとクライストの対話は、私の創作ですが、実際にあったとしてもおかしくないわけで。年表を作るのも大変でした。
松永 通貨のターラーやグルデンの価値も、確定するのが難しいですね。
逢坂 あれは結局、あいまいなままでした(笑)。たまたま見た本に、当時の諸物価が書かれていたので、そこから類推したりして。距離の単位も、今とは違います。
松永 当時のプロイセンマイルは、今のマイルより長いですよね。
作家、音楽家、法律家ホフマン
逢坂 ホフマンの小説は、日本では昭和初期から十年代にかけて、断続的に翻訳されています。戦争直後には、粗悪な仙花紙(せんかし)本でも出ているんですね。私も古本でずいぶん集めました。対訳本も出ていたくらいで、日本でも人気があったわけです。ドイツでは、ホフマンの没後は次第に読まれなくなったようですが、フランスで評判になり、ロシアにも波及していきました。
松永 日本では、ドイツ文学通の方が特にお好きですね。「砂男」とか個々の作品は、ドイツで今でも読まれているようです。アンソロジーに入ったり、子供向けに書き直されたりもしていると思います。ただ、ホフマンって、ドイツではすごく多い名前なんですね。
逢坂 鈴木や佐藤みたいな。
松永 そう。それで、イニシャルのETAもつけて呼ぶことが多いです。
逢坂 ゲーテが、ホフマンに対して批判的だったんですね。判官贔屓じゃないけど、私はゲーテばかり持て囃されるのが腹立たしくて。だから、この本の中では、ゲーテをかなり批判的に描いています。といっても、私の創作じゃありませんよ。実際にあったエピソードばかりですから。
松永 ゲーテはロマン派に否定的でしたからね。でも、何でもゲーテじゃ面白くないですよ。私はホフマンが脊髄癆で亡くなったのも知らなくて。作家であると同時に、音楽家で法律家だったというのは知っていましたが、奥さんの名前やユリアという少女とのエピソードも知りませんでした。
逢坂 作曲家としてのホフマンは、モーツァルトの亜流みたいな感じなんですね。なんとなくモーツァルト、とでもいうか。
松永 チャイコフスキーの「くるみ割り人形」は、ホフマンの原作ですね。シューマンにも、ホフマンの作品に曲をつけたものがあります。
逢坂 ベルリンに取材に行った時に、ちょうど「くるみ割り人形」のバレエがあると聞いて、劇場に行ったんですよ。礼服も持ってないから、どうしようかと思ったけど。
松永 そんな心配はしなくて大丈夫ですよ(笑)。みんなジーパンとかで来てますから。
逢坂 やっぱりチャイコフスキーになると、メロディが耳に残るんですね。その点、ホフマンは、残念ながらそこまでは行かない。代表作の「ウンディーネ」も聴いたけど、耳に残らないんです。才能がないわけではないけれど、音楽家としては大成しなかった。
松永 ライバルが大きすぎたのでしょうか。ベートーヴェンと張り合うのは、ちょっと大変です。でも、ホフマンは法律家としても、正義感が強くて筋を通す、魅力的な人ですね。
逢坂 その代わり、苦労も多かった。特にお金に苦労して、安定したのはやっと最後の数年ですか。その五、六年で、集中して小説を書いています。
秘密が多すぎる!
松永 どんなふうにホフマンを小説にするのかと思ったら、この設定が素晴らしいですよね。ホフマンにまつわる手記を誰が書いたのか、それが現代の日本にどのように繋がってくるのか、そういった謎で最後まで引っ張られます。出だしはスペインで、ギターがらみというのも逢坂さんらしいし。
逢坂 あれは、本間鋭太なる人物が書いて送ってきた原稿でありまして、私が書いたわけでは......。本間が私の関心を引くために、ギターの話から始めたんですよ。
松永 そうでしたね(笑)。その本間鋭太による翻訳と解読が、すごく面白いんです。最初はホフマンについての手記は、前半しかないという話だったじゃないですか。その前半が終わりになった時には、自分でもがっかりしてしまって。続きがあると分かった時には嬉しかったですね。
逢坂 あのくだりに出てくる、本間道偉という医者やその係累は、実在した人物なんです。本間鋭太の本間は、それなりの理由があってつけた名字ですが、先祖の道斎は単なる思いつきでした。偶然とはいえ、古い雑誌に載っているのを見つけて、自分でも神がかってるな、と驚きました。
松永 ホフマンの部分と、ミステリー要素の割合がすごくいいですね。だんだん倉石家の方にも複雑な秘密があることが分かってきて、しかもそれがホフマンと重なってくる。
逢坂 最初からこんな仕掛けにするつもりで書いた覚えはないんですけどね。
松永 これは秘密にしてくださいって、倉石家の人たちがみんな、沙帆さんに言ってくるでしょう。倉石家、ちょっと秘密が多すぎるんじゃないかと。
逢坂 ドイツ語については、おかしなところはありませんでしたか。
松永 これは突っ込むところかどうか分かりませんが、いわゆるシーボルトを「ジーボルト」だとお書きになっていますよね。標準ドイツ語では確かにジーボルトなんですが、南ドイツに行くとSの発音が澄んだ音になるんです。それで日本語でもシーボルトになったのかも。本人がどう発音したかは分からないので、正解は分かりません。
逢坂 北と南で発音が違うのは知っていたんですが。ただ、正しくはジーボルトじゃないか、とする少数意見を紹介したい、という気持ちがあったんです。
松永 本間鋭太がまた不思議な人で、服装もいつも奇天烈なんですね。変なステテコだったり、急におしゃれになったり。アパートに鍵をかけないくせに、一番手前の部屋に貴重な本が置いてあって、大丈夫なのかと。
逢坂 あそこに出てくる『カロ風幻想作品集』の初版本は、私が手に入れたものなんですよ。神保町にある洋書専門の古書店の目録で見つけて。それをそのまま使いました。たぶん、私が持っている一番高い本ですね。本物か偽物かは、鑑定団にでも出さないと分からないけど。
松永 当時の本の初版部数が、どのくらいだったか分かりませんが、その後、戦争もありましたし、そのうち何冊が残ったかと考えると貴重ですね。
逢坂 折れ目とか染みもなくて、状態のいい本であることは確かです。
ドイツへ、弁天町のアパートへ
松永 執筆にあたっては、ドイツにも取材に行かれたのですね。
逢坂 バンベルク、ライプツィヒ、ベルリンの三か所ですね。ホフマンが長く住んだバンベルクは、中世そのままのたたずまいが残っていて、いい町でした。当時、ホフマンが住んでいた家が、記念館になっていてね。マッチ箱を立てたような小さな家で、そこの三階と屋根裏部屋を借りて、ホフマン夫妻が住んでいたんです。境い目の床に、上と下で話のできる穴が、残っていましたね。
松永 私はバンベルクはまだ行ったことがないんです。
逢坂 ライプツィヒは、ホフマンも森鷗外も、ゲーテもいたことのある町です。彼らが行った居酒屋がありましてね。
松永 ああ、『ファウスト』で有名な。
逢坂 クライストが人妻と心中した、ベルリン郊外のヴァン湖(ゼー)にも行きました。小さなお墓があってね。何もあんなところで死ぬことはないじゃないか、と思いましたが。
松永 本間鋭太の弁天町のアパートにも行きたくなりますね。本間や沙帆は、あれからどうなってしまったのか......。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、『鏡影劇場』という題名にも、二重の意味が込められているように思います。二度おいしいというか、ホフマンのことがよく分かるし、ミステリーとしても、最後に何回も驚かされました。まだあるの、まだあるのって。
逢坂 それで結末を袋とじにしたんです。昔はよくあったんですよ。封を切らなければ、お代はお返ししますって。今回は返金はしませんが。松永さんのようなドイツ文学者に読んでいただいて、面白がってもらえれば、書いた甲斐がありました。読者がみんな松永さんのように喜んでくれるなら、作者の本間鋭太も本望でしょう。
(おうさか・ごう 作家)
(まつなが・みほ 早稲田大学教授/ドイツ文学翻訳家)
最新の対談・鼎談
-
2026年2月号掲載

内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念
階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない

意味ある敗北とは何か―アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉―
-
2026年1月号掲載

『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』刊行記念鼎談
ひのえうまに生まれて生きる私たち

ひのえうまに生まれて―300年の呪いを解く―
-
2026年1月号掲載

三島由紀夫生誕100年記念対談
私たちの中に生きている三島

三島由紀夫論
-
2025年12月号掲載

『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念対談
池上さんと村上さんが話す前に考えていること

池上彰が話す前に考えていること