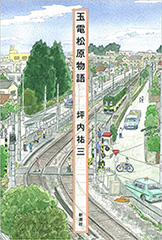書評
2020年11月号掲載
坪センパイの世田谷
坪内祐三『玉電松原物語』
対象書籍名:『玉電松原物語』
対象著者:坪内祐三
対象書籍ISBN:978-4-10-428105-3
坪内祐三さんに初めてお目にかかったのは今から十五年ほど前だが、そのときどんな話をしたのかはまるで記憶にない。とにかくちょっと怖かったことだけ覚えている。辛辣な話をするのも冗談を言うのも表情と声のトーンがいっしょで、怒っているのか上機嫌なのかさっぱりわからないからだ。
それが何度めかにお会いしたときに一変したのは、私が赤堤(あかつつみ)小学校で坪内さんの一学年後輩だとわかってからだ。坪内さんはうってかわってにこにこしながら、当時の赤堤周辺の思い出話をすごい情報量と熱気で語りだした。私が住んでいた社宅まで言い当てられたのには驚いた。私の書いたものから推理して割り出したのだそうだ。楽しそうだった。そのときから私の中で「坪内さん」は「坪センパイ」に変わった。
私たちが赤小に通っていた当時の世田谷のあのあたりは、それはもう大した田舎だった。そこらじゅうに畑があった。道路は舗装されていなかった。赤小の裏手には牧場まであって、廊下の窓を開けると牛と目があった。でも、私は年を追うごとにあれはぜんぶ幻覚だったんじゃないかと思うようになっていた。私の記憶の不確かさと、人としての信用度のなさから、当時の話をしても誰にも信じてもらえなかった。「まさか、都内に牧場なんかあるわけないでしょ」と言われれば、「ですよねー」と気弱に引き下がっていた。
けれども坪センパイは超人的な記憶力と地理感覚でもって、私のあやふやな記憶を一つひとつ裏付けてくれた。私が近所にあった店や場所のあいまいな思い出を自信なさげに口にすれば、「ああ、あそこね」と脳内の地図と即座に照合してくれて、おまけに「あの店の店主はじつはね......」などといったトリビアまで授けてくれた。
極めつきは「べぼや橋」だ。私が住んでいた社宅の近くをドブ川が流れていて、川向こうに行くにはいつもその橋を渡っていたのだが、家族の誰に聞いてもそんな橋は知らないと言う。グーグルで検索しても自分の文章しかヒットしない。それを確かに「あった」と請け合ってくれたのも坪センパイだった。
坪内さんとの世田谷談義は、私にとっては心おどる「答え合わせ」の時間だった。センパイの「ああ、あそこね」のたびに、頭の中で曇りガラスのようにぼんやりしていた記憶のピントが合い、色が戻り、地図上の確かな一点として定着した。
『玉電松原物語』は、その答え合わせの文字バージョンだ。とちゅう出てくる懐かしい固有名詞に、何度も大きくうなずいた。センパイの出たマリア幼稚園には私の妹も通っていた。当時は洒落たショッピングセンターだった経堂ストア。レイク・ヨシカワは、私が初めて筒井康隆の本を買った書店。OSK(大阪松竹歌劇団)の振付師だった赤小のW先生(運動会の演(だ)し物(もの)の集団演舞は、今思えば小学生に要求するレベルのものではなかった)。
驚かされるのは、小学生とは思えない坪内さんの行動半径の広さだ。たとえば当時の私にとって世界とは、赤小と自宅を起点に玉電山下駅までと経堂駅までですべてだったが、坪内さんはその何倍もの広域を自分の庭とし、さらに玉電や自転車を駆使して三軒茶屋や下高井戸にまで版図を広げていたのだ。
坪内さんは、まるで筆を散歩させるように、連想の赴くままにつぎつぎ思いついたことを書いていく。そのゆるやかなリズムに、こちらも昭和の世田谷をいっしょに散歩しているような心持ちになる。それにしても坪内少年はつくづくヘンだ。古本屋めぐりや焚き火や花見など、趣味が小学生と思えないほど爺くさかったり。セキセイインコを五十羽も飼っていたり。肥満児で一日に牛乳を二十本飲んだり。野球少年でプロレス小僧でマンガ少年で。ワルガキでおたく、自由で博識で社交の達人。もしも小学生当時、私が坪センパイと知り合いだったらどうだっただろうと想像せずにいられない。もっともセンパイは、「おれはもちろん君のことだって知っていたぜ」と眉をひこつかせながら言うのだけれど。
読んでいて、ふと愕然とする。こんなふうに紙と文字ごしに「答え合わせ」をするしかなくなってしまったことに。私の地図は、まだまだらに曇りガラスのままだ。坪センパイ、学校の向かいにあったグライダー工場のことはどうなるんですか? べぼや橋のことも、連載が続いていれば書くつもりでしたか?
最後に美しい玉虫の死骸のことなんか書いて、それきりいなくなってしまって、坪センパイは本当にひどい。