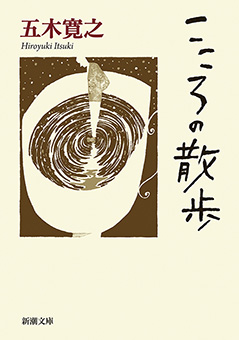書評
2021年4月号掲載
「時代の風」を感じるレーダー
五木寛之『こころの散歩』
対象書籍名:『こころの散歩』
対象著者:五木寛之
対象書籍ISBN:978-4-10-114735-2
私が五木寛之さんのエッセイに触れたのは、中学生だった1980年頃で、たぶん文春文庫の『深夜草紙』だったと思う。当時は野坂昭如、井上ひさし、北杜夫、遠藤周作らのエッセイが文庫に入っており、小説よりも先にそれらを読むことが多かった。
五木さんのエッセイは小説や作家、旅や歌について自由気ままに語られていて、漠然とした憧れを抱いた。その後、古本屋で「話の特集」「面白半分」などの雑誌を探して、エッセイや対談を読んだ。
最新のエッセイ集である『こころの散歩』を読んで、その頃の印象と変わらないことに驚く。八十代の後半となって、老いや死が大きなテーマとなっているが、何かに凝り固まったり説教くさくなったりせず、その筆致は若々しい。新型コロナウイルスの流行の影響さえ、夜型から昼型の生活に移行したという前向きの変化としてとらえられている。
本書で嬉しいのは、交流のあった作家のエピソードが豊富なことだ。坊主頭の今東光が、長髪だった五木さんとすれ違いに放つ一言。松本清張に「ぼくは日本のH・G・ウェルズをめざしているんだ」と云われたこと。埴谷雄高に社交ダンスのステップを見せられたこと。
泉鏡花賞の選考会でのエピソードもいい。受賞作がなかなか決まらないなか、石和鷹の『野分酒場』を推す三浦哲郎が、「うーん」と深いため息をつき、それが受賞を決めた。吉行淳之介は「三浦のため息は、芸だね。説得力がある」と云う。
ラジオ番組で「歌う作家たち」という特集を組んだ話も面白い。三島由紀夫、石原慎太郎、戸川昌子、新井満がリリースしたレコードを紹介する。そして野坂昭如が「マリリン・モンロー・ノー・リターン」でオオトリを務める。
その野坂が主催した宴会で、五木さんは朗詠をやらされる羽目になる。彼が亡くなった際には、同期デビューの野坂がいるから自分は仕事を続けてくることができたと感謝する。
「彼と反対の方向へ歩いていけばいいのだ、と自分に言いきかせていたからである」
著名人だけでなく、大陸浪人の風格を持つ画家のKさんら、さまざまな場所、時代に出会った「一言一会の人びと」についての短い回想が印象的だ。だれか、五木さんの人物エッセイだけ集めた一冊を編んでくれないだろうか。
早稲田大学に在学中、中野にあった音楽喫茶〈クラシック〉に通った話も出てくる。入り口で喫茶券を買って、崩れ落ちそうな階段をのぼって二階の席に座り、何時間も過ごす。オーナーは画家で、〈ルドン〉という酒場も経営していた。
ロシア文学科で五木さんの同級生だった作家の川崎彰彦も、この二店の常連だった。川崎さんの最後の小説となった『ぼくの早稲田時代』(右文書院)では、五木さんをモデルにした人物が登場する。縁あって同書を編集した私が、五木さんに序文を依頼すると、旅先から友情に満ちた文章を送ってくださった。
本書で五木さんは、自分の記憶に固執している。それは、「歴史は選択的に相続されたものの集積」であり、そこからこぼれ落ちた記憶こそが重要なのだという信念に基づくからだ。上澄みの部分でつくられる「正史」に抗う人びとを、長篇小説『風の王国』で描いた作家らしい言葉だ。
そして、父や母から目に見えるモノではない、生活習慣やものの考えかたを「相続」していると書く。
「若い頃は、その相続しているものに反撥したこともあった。しきりに言われていた『絆』とは、私たちの世代にとっては切り放すべき重い鎖のように感じられていたのである。しかし、あえて絆を求めることはない。切っても切っても切れないのが、絆というものなのだから」
あるエッセイに出てきた人物が、別のところにもひょっこり顔をのぞかせる。ひとつのエピソードがリフレインされ、より深く語られる。それが雑文集の魅力だ。
最初の雑文集に、ボブ・ディランの歌詞から『風に吹かれて』と命名した理由を、「雑文は時代の風に吹かれて、散り散りに飛んでいってしまうところに命がある」からだと、五木さんは云う。
五木さんにはきっと、時代の風を感じるレーダーが備わっているのだろう。そのレーダーは、過去にも未来にも向けられている。
(なんだろう・あやしげ ライター・編集者)