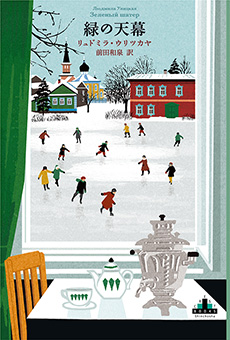書評
2022年1月号掲載
文学への愛と信頼からなるアンチ教養小説
リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』(新潮クレスト・ブックス)
対象書籍名:『緑の天幕』(新潮クレスト・ブックス)
対象著者:リュドミラ・ウリツカヤ/前田和泉訳
対象書籍ISBN:978-4-10-590177-6
現代ロシアを代表する作家のひとりリュドミラ・ウリツカヤの畢生の大作といえる『緑の天幕』がついに日本語に翻訳された。ウリツカヤは、ソ連時代を生きたさまざまな家族の姿を、機知に富んだ筆致でこまやかに描くのを得意とし、ロシア語読者に絶大な人気を博している。最近は毎年ノーベル文学賞の上位候補に名前が挙げられ、国際的な知名度も高い。
本書は、スターリンが死んだ一九五三年から亡命詩人ブロツキーの亡くなった一九九六年までの四〇年あまりの間、自由を制限され抑圧された反体制知識人たちが何を考え、どう振舞ったか、その生きざまを丹念に描いた心震える傑作である。
物語の中心は、一九四三年生れの著者とほぼ同年代の幼なじみ、三人の男だ。陽気で如才なく商売気もあるイリヤは、カメラを贈られたことから「時代の証拠」である写真を自ら撮るようになり、やがて禁止されていた前衛絵画を集め、サミズダート(自主的な地下出版)に携わるようになる。繊細な詩人の感性をもつ孤児のミーハは、ユダヤ人ゆえの差別を受けながらも聾啞者教育に打ち込もうとするが、発禁小説を読んだことを密告され職場を追われてしまう(このあたりはウリツカヤ自身がサミズダートに関わったために遺伝学研究所を辞めさせられた事実を想起させる)。一九世紀前半に皇帝の専制に反旗を翻した貴族=デカブリストの末裔にあたるサーニャは、いじめっ子に手を切られ、ピアニストになる夢をあきらめざるを得ず、音楽学者への道をめざす。
この三人に加え、さらに同世代の女が三人登場するが、そのうちのオーリャも物語の重要な役割を担う主人公である。母親は頑迷な体制派ジャーナリストだったが、オーリャ自身は反体制の教師が投獄されたとき署名をして大学を退学させられ、その後イリヤと出会ってサミズダートの作成に協力することになる。このように一言で反体制知識人といっても、育った環境も違えば関心もまちまちだ。いったい彼らに共通していたものは何だったのか。
少年三人を結びつけたのは、文学の教師シェンゲリの存在である。地下文書だったパステルナークの『ドクトル・ジヴァゴ』を読む反体制派のシェンゲリ先生が、ロシア文学への絶対的な愛と信頼を生徒たちに伝授し、それが生徒たちの血肉となり人間性を形づくったのだ。彼は生徒たちにこう語りかける。「文学は人類が持つ最良の宝です。そして詩は文学の核心で、世界と人類の中にある最良のものすべてが凝縮されています。それは、魂にとって唯一の糧です」。まさに「文学中心主義」のロシア知識人ならではの熱い言葉である。
そして、それを具現化するかのように、テクストのそこかしこにロシア文学からの引用、言及、暗示がちりばめられ、プーシキン、レールモントフ、クズミン、チェーホフ、ツヴェターエワ、アフマートワ、マンデリシュタームらが綺羅星のごとく連なり、プロットから独立した第二の物語空間を築いている。登場人物と同じくらいたくさんの作家や詩人の声が通奏低音のように流れているのだ。これを「間テクスト性」と呼ぶとしたら、本書は間テクスト性の網目の上に成り立つ大河小説であるといえるかもしれない。また、多数の登場人物の心理を丁寧に描写してドラマを組み立てていく手さばきから、ウリツカヤを「現代のトルストイ」になぞらえることも誇張ではあるまい。
『緑の天幕』は、師弟愛と友情と文学の魅力が溶け合わさった作品だが、人間の成長を描いた単純な「教養小説」かというと、けっしてそうではない。というのも、もともとアイロニカルな「イマーゴ(=成虫)」というタイトルがつけられていたとおり、作中、未熟な知識人が、成虫になれない幼虫に喩えられているのである。ウリツカヤは最初から「アンチ教養小説」を想定していたのではないかと思う。
しかし、のびのびと成長することの許されない強権的・抑圧的な社会において、そもそも人間の正常な成熟が望めるのだろうか。人間の成熟を促すような開かれた自由な社会とはどのようなものなのか――それは、現代の私たちにとってもきわめてアクチュアルな課題であるはずだ。
(ぬまの・きょうこ ロシア文学者)