書評
2024年10月号掲載
伊与原 新『藍を継ぐ海』刊行記念特集
孤島で千二百万年を思う
対象書籍名:『藍を継ぐ海』
対象著者:伊与原新
対象書籍ISBN:978-4-10-336214-2
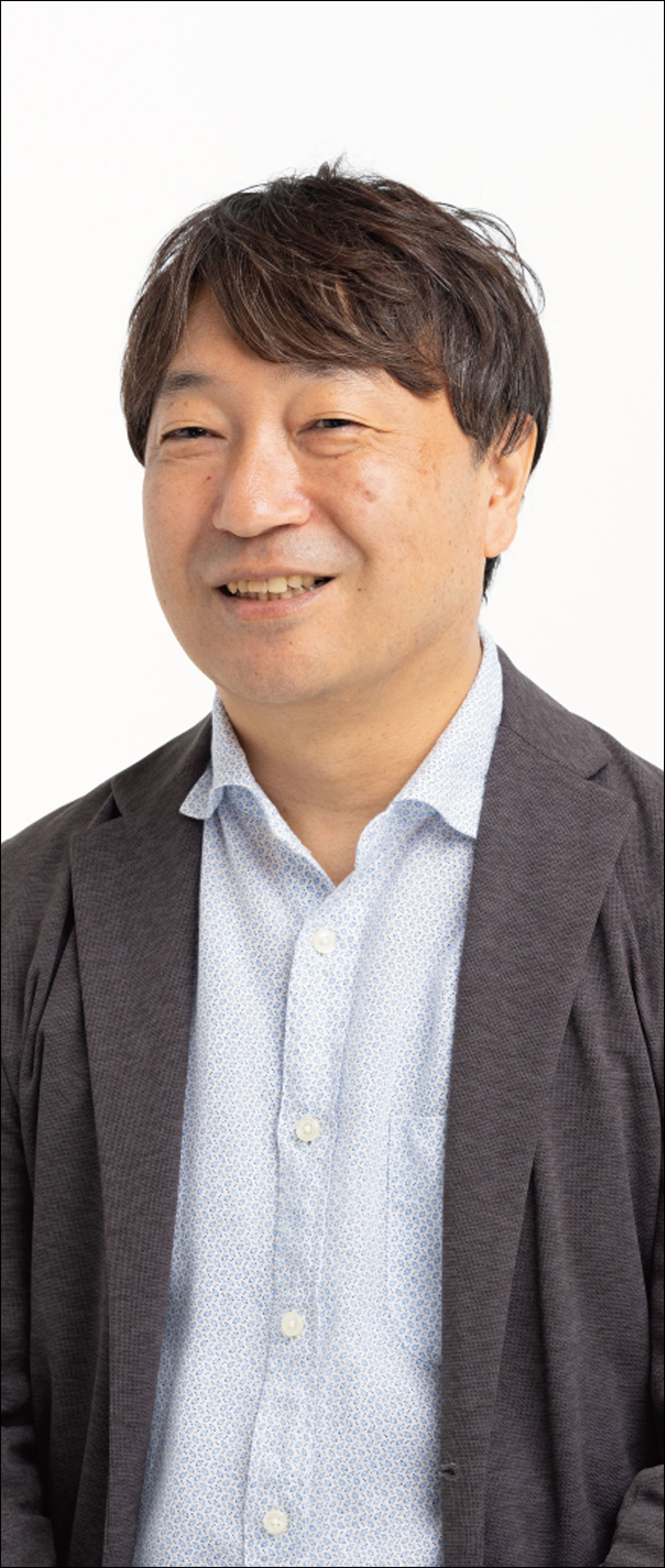
地質学者がいう“最近”という言葉は、もはや一種のジャーゴンとなっている。ある地質現象について彼らが「これは最近の出来事で」と説明を始めたとしても、鵜呑みにしてはいけない。よくよく聞けば百万年前の話だったりするのはざらだからだ。数十億年にわたる地球史を読み解くことを仕事にしている以上、当然といえば当然かもしれない。
百万年前が“最近”なら、日本列島に人間が住み着くようになった四万年前は“つい最近”ということになる。そんな時間感覚で日常を生きることは不可能だとしても、ときに時空を俯瞰して今自分が立っている位置を眺めてみることは、精神の深呼吸とでもいうべき効果をもたらすのではないか。
日本海の孤島、見島で、岩場に建つ観音堂から高さ三、四十メートルはあろうかという断崖を見上げながら、私はそんなことを考えていた。
褐色のごつごつした岩肌は、およそ千二百万年前に海底から噴き出した溶岩と火山噴出物である。目を凝らせば、ラグビーボールのような形をした火山弾がいくつもはさまっているのが見て取れる。それらの地層を斜めに横切るようにして、灰色の岩石が貫入している。それもまた、地下深くから上がってきたマグマが冷え固まったものだ。
見島へは、『藍を継ぐ海』の第一編、萩焼を題材にした「夢化けの島」執筆のための取材で訪れた。山口県は萩の北西約四十五キロメートル沖にぽつんと浮かぶ、人口六百人ほどの小さな島である。4月の海風を全身に受けながら、観光協会で借りたレンタサイクルで、丸一日かけて島を一周した。
見島の成り立ちは、実は日本列島の誕生と深く関わっている。およそ二千万年前から千五百万年前にかけて、アジア大陸の東縁が割れて隙間に海が広がっていき、日本列島が現在の位置まで移動してきた。見島は、そのとき日本海の海底にできた裂け目から噴き上がってきたマグマが作り出した火山島なのだ。
この島では、萩焼に欠くことのできない原土の一つ、「見島土」が採れる。千二百万年前の溶岩が風化してできた、赤い粘土である。一説には、島流しの憂き目にあった江戸期の名工、六代林半六こと林泥平がこの粘土を本土に持ち帰り、以降萩焼で広く用いられるようになったという。
見島土は、いわば列島誕生の副産物であり、大地が経てきた時の賜物だ。林泥平も、彼に続いた萩の陶工たちも、当然そんなことは想像だにせぬまま、その赤い粘土を用いて器を挽き続けてきた。褐色の断崖と対峙して泥平が考えたことは、悠久の時の流れなどではなく、この島の何がどう使えるか、であったはずだ。
日本人の祖先が列島へ渡ってきて、四万年。世代に換算すれば、ざっと千三百世代である。列島の各地に広がった人々は、多様な風土に適応し、山海の資源を活かす術を学んで定着した。そして、その方法を家族や共同体で連綿と受け継ぎながら生きてきた。『藍を継ぐ海』では、見島の他に、奈良の東吉野村、長崎の長与町、北海道の遠軽町、徳島の海辺の町を舞台にしたが、この五編に通奏低音として響かせようと試みたのは、それぞれの土地に固有の「継承」である。
継承の際の理屈としては、時代に応じて様々なものが使われてきたであろうが、現代を生きる我々は「科学」という理屈を知っている。人類の飽くなき好奇心が生み出した、今のところもっとも強力な理屈である。科学のせいで世界から神秘が失われたと嘆く人々がいることは知っているが、私はその考えに与しない。
神代の物語を紡いだ人々は、天の川銀河の二千億個ともいわれる恒星系の一つで地球が四十六億年前に生まれたことを想像できただろうか。流れ星で吉兆を占った人々は、その正体が彗星の塵や小惑星の破片であることを想像できただろうか。村の浜でウミガメの産卵を見守ってきた人々は、それらが遥か太平洋をひと巡りして戻ってくることを想像できただろうか。
科学が世界を味気ないものにしているのではない。科学の知識が積み上がるにつれ、世界の時空はむしろ拡大し、その細部も豊かなものになっているのだ。列島の各地で営まれてきた「継承」を科学の光で照らしたとき、その像はよりくっきりと浮かび上がり、また新たな輝きを放ち始める。
そんな時代に生きる幸運を噛みしめながら、千二百万年に及ぶ地球のダイナミクスが作り上げた断崖を眺めていると、見島の海風が胸の奥まで吹き通っていくように感じた。
(いよはら・しん 作家)








